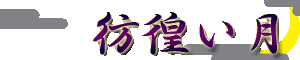夢の中で目を覚ます
夢の中で目を覚ます。
変な表現だけれど、いつしかそれが普通になった。
今日は、室内。
和室。
趣がある、まるで文化財のような部屋。
確か、彼の仕事部屋。
今日は彼はそこにいない。
くるり、見回して、壁をすり抜ける。
さすが夢、と言うべきか。
この夢の中で私はモノに触れるか否かを自在に選べる。
そして、夢の中の登場人物に姿を視認させる、させないの選択をすることができる。
まるで幽霊か妖怪にでもなった気分だ。
ただ、視認させたくてもできない人もいるし、視認させたくなくても勝手に私を見られる、いわゆる鈍い人、鋭い人、というのは往々にしているようなのだけれど、そこを追及する気はさらさらない。だって夢の中だもん。
いくつかの部屋を覗いて、彼が自身の寝室で伏せっているのを見つけた。
全身を包帯で巻いているミイラのような細身の和装男。
名前は知らない。
けれどよくよく私の夢の世界では登場する彼は、鋭い人、に分類される。
初見なんて、出会いがしらに丸い球みたいなのぶつけられた。
そこで現実で目を覚ましてしまったので、あの後彼がどんな反応をしたかは知らない。
二回目が、まさにこんな感じで寝込んでいた。
彼は何度かに一度は必ずこの状態だ。体が弱い人なのかもしれない。
「また調子悪くしたんだ」
近づいて、そばに腰を下ろす。
額に置かれている手拭いが水を吸ったままという乱雑なものなので、近くに置いてある水の張られた桶に突っ込んで絞ってから乗せてやる。
もう一つ、脇に置かれていた手拭を濡らして、固く絞ってから丁寧に包帯の上から体を拭く。
寝込んでいる時くらい包帯を外せば発汗が良くなるものを。
以前呆れてもの申せば、都度総とっかえなどしていられない、などと呆れ返されたのだが、そういう問題ではないと思う。
うっすら、彼の瞼が持ち上がる。
ほんやりした、白めの部分が黒ずんだ変わった色の瞳が彷徨ってから私を見つけた。
「やれ、また、来やったか」
ぽつりと呟いて、咳き込む。
「また、風邪?懲りないね」
咳き込んで丸くなった背中をさする。
ヒュゥ、と喉から乾いた音。
喘息の人が出す音によく似ている。この人、気管支も弱いんだろうか。
痰の絡まったような音に変わったのに気付いて、摩っていた手を丸め、とんとん、と叩く。
いつの間にか取り出していた紙に痰を吐いて、彼は息を落ち着けた。
「現れるたびわれの世話を焼くとは、まこと、おかしなあやかしよ」
彼はどうやら私を妖怪の類として認識しているらしい。
まぁ自分が夢の中でできることを思い返してみれば違いない。
「おかげさまで私の看病スキルがメキメキ上達しているよ」
もう少し寝なよ、と目元に手をかぶせる。
小さく頷くように動いた頭。すぐに聞こえる熱のこもる、けれど、穏やかな息。
珍しく素直ね、なんて口から出そうだったけど、起こしそうで止めた。
ゆるゆると流れる時間。
鳥が囀り、風が木々を撫ぜる、自然の音。
夢の中の穏やかな時間が好きだ。
しばらくして、どすどすと床を踏み抜かんばかりの足音が聞こえた。
あぁ、この足音は。
スタン
断ることもなく障子を開け、迷うことなく私に向かって刀が振り抜かれるのを透過することで避ける。
銀の光。
いまだにその顔を拝めたことがないので、私はそれをそう呼んでいる。若干厨二臭いがそうとしか表しようがないから仕方ない。。
あの足音の主は決まって現れると同時に私に切りかかる。
そして、それと同時にまぶしさを感じて目を開けるのだ。
直後、衝撃。
「いだっ」
「いつまで寝ている」
数学教師に頭を教科書の角で殴られた。暴力反対。
かといって口答えしたところで授業開始まで寝ていた私が悪いし、言い負かされるのは必須なので、スミマセンと片言で謝った。授業中でないだけセーフだ、セーフ。
※バックブラウザ推奨
2014.01.08