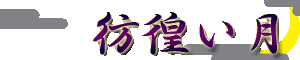掌で転がる
別に告白なんてしたつもりはなかったんだ。
いや、こう、刑部さんだったころよりも穏やかでやさしくなった吉継さんは、女子高生卒業したての未成年からしたら魅力的なわけですよ。今まで見てきた同学年の男子なんか目じゃないくらいに魅力的なわけですよ。ちょっと怪しげだけどそれは元からなので差し引いておく。
けれど、この年の差、となれば親兄弟にしか見られていないのかな、と思っていて、そういう範疇外かと思って聞いた質問が、なんだかんだありながらも、まさかの熱烈な告白で帰ってきて…。
そこまで思い出したところで、その熱烈な告白が耳元で蘇る。
――女などしかいらぬ、幼かろうと、熟れていようと、われが欲するはぬしだけよ。
あんな、優しい、熱がこもった声で言われて、混乱しない訳がない。
あの後、石田先生が入ってきてくれたから、とりあえず逃げ帰ってきたけれど、
「猛烈に、顔を、合わせづらい!!」
布団に突っ伏して、声にならない声を上げる。
夢の中で会っていた時にそんな言葉も、声も聞いたことがなかった。
時々顔を合わせては看病したり、庭でぼけっとしたり、とりとめのない話をしたりするくらいで、そんなドラマや映画のような空気になんて一回もない。
確かに、夢の中で目が覚めたときは、ついつい姿を探していたけれども。
ちらり、部屋にかかっている時計を見る。
いつもはお見舞いに行っているはずの時間。
だが、昨日の今日で、どんな顔をして会えばいいのだろう。
うぅ、と呻いて、自分のうめき声以外にも音を発している何かに気付く。
「あれ、」
携帯がバイブっている。
知らない番号だ。
とりあえず、間違い電話だろうと無視をしていれば鳴りやむ。
……そして物の数秒と経たずに同じ番号からかかってきた。
え、何この鬼電。あ、間違い電話だと気づかずに通じないと焦ってかけまくっているのかもしれない。それはかわいそうだと電話をとれば。
『遅い、さっさと出ろ愚図が!!』
きーーーーん、と耳に響いたのはなぜか石田先生の声だった。
「ちょ、ちょ、先生なんで!?私の番号…!!」
『貴様どこで油を売っている、さっさと来い』
「え、ど、どちらまで…?」
『刑部の病室に決まっているだろう』
「え、なんで…」
『さっさこい、拒否はない』
「ハイ…」
言うこと言って返事も聞かずに切られる通話。
いや、何故、石田先生が私の番号を……、もしや職権乱用ですか先生。
しかし、先生なら考えられる…。
あの刑b…いや、吉継さんにかける情熱と言ったら前世を凌ぐ。
クールビューティで頭脳明晰な先生は、時折とてつもなく残念である。今に始まったことではないのだが。
ぶちぶちと文句を連ねながら、しかし確実に出かける準備を整える。
春休みながら、今日は土曜日。家にいた母に声をかけて玄関を出た。
心地よい春の日差しを受けて、ふと、夢の中の出来事を思い出す。
同じように心地よい日差しの日だった。
「ぬしは物を食いやるのか?」
ちょうど休憩時間だったのだろう。
お茶をずずっとすすりながらそんなことを彼は言った。
寝ている間に食べ物を食べるか、考えなくても明白である。
それにおなかがすいたら目を覚ます。
「食べる必要がない、かな」
この幽霊のような妖怪のような状態では、これが一番妥当な表現だった。
「ふむ、食欲がないと」
「いや、それはあるけど」
「なれば、ほれ」
すいっと綺麗に長方形に切られた羊羹を出された。
食欲はあるけど食べられない訳ではない、と取ったのだろう。
夢の中で、物を食べるとどうなるんだろう。
「やれ、」
何かを言いかけたらしい彼を無視してぱくりと食べてみた。
甘い、気がする。
もぐもぐ、ごくん、と咀嚼して飲み込んで、でも腹に入った気がしないのは、やっぱり寝ている最中だからだろう。
「食べた気がしない」
「……ヒヒッ、さようか」
「何、嫌いなの、羊羹?」
「いや?」
私に差し出すくらいだから、嫌いなのかと思えばそういうわけでもないらしい。
ふぅん、と適当に返事をして寝転がった。
ずりおろされた包帯の口周りに羊羹が運ばれて消える。見た目はミイラなのに、仕草はドラマで見る上流貴族のようなそれ。
変な人だなぁ。人かも怪しいけど。
猫のような、それでいて少し変わった色彩の目が緩むのを見て、もしかして好きなのかな、羊羹、などとぼんやり思って、そのまままどろむように現実で目が覚めて猛烈に羊羹を食べたくなった。
回想に浸りながら、気付けば病院にきちんと向かっていたらしい。
病院の自動ドアが開き、独特の薬臭を運んできた空気でそれに気づいた。
そういえば、前回機嫌を損ねたときに、次に好物買ってくる、と約束をした。
売店によって、安物で悪いが羊羹を買う。
それから病室に顔を出せば、吉継さんがぱちくりと瞬いた。
「やれ、ほんにきよったか」
病室に、石田先生はいない。
「吉継さん、先生は?」
「ぬしを呼びつけた後に帰ったわ」
「あのハシビゴロウ…!!」
「ヒヒッ、ハシビゴロウか…ヒヒヒッ」
呼び出しておいて、放置とは。
恩師だからとなんでもして良いわけじゃないんだぞ。
そんな思いを込めて吐き出した学生時代の裏のあだ名に吉継さんが吹き出す。
ヒィヒィ笑ういつも通りの吉継さんに、なんだか緊張して損した、と息をつく。
それから袋を押し付けた。
「なによ?」
「ロリコン扱いしたお詫び」
「ほう、覚えていやったか」
がさりと遠慮なく袋から羊羹を取り出す吉継さんは、それを取り出して、首を傾げた。
「ぬしに、言うたことがあったか?」
何を、と聞き返そうとして、それが羊羹を指していることに気付いた。
よかった、何も考えずに買ったけれど、今生でも彼の好物だったらしい。
「言ってはないけど、なんか幸せそうに食べてたじゃん、昔」
「……ああ」
あのときか、と嬉しそうに呟く。物覚えいいなぁ。
その表情のまま羊羹をぱくりと食べる。コンビニでも売っているような100円もしない羊羹なのにそんなにおいしそうに食べるなんて。
本当に好きなんだなぁ、羊羹。
それを見ながら同様に売店で買ったお茶を飲む。
羊羹を食べ終えた吉継さんがこちらを見た。
「茶が飲みたい」
「えー、もうしょうがないなぁ、買ってきてあげようじゃないか。
なんか好みある?」
「ぬしのソレでよかろ、くれやれ」
ヒヒッ、と意地悪く笑う吉継さんは、私の手にあるペットボトルのお茶を指す。
おい。おっさん、おい。
吉継さんと、ペットボトルを見比べて、はぁ、とため息ひとつついて差し出した。
はるか昔に羊羹あーん、をしているのだから、これくらい。
迷いもなく口づける彼は、意識しているのかしていないのか。
「…ねぇ吉継さん、私がドン引くとか思わなかったの?」
主語はないけど、間接キスではなく、昨日のことだときっと察しはついたのだろう。
「ヒッヒ、何を言うか。われの守備範囲内で嬉しかろ?」
悪びれもなく笑いながらペットボトルを傾ける。
守備範囲というか、範囲っていうか、ピンポイントだったよね…、私オンリーという名の。
「それになァ、」
ちゃっかりペットボトルを空にして、私にずいと近づく。
反射的に身を引くが、いつの間にか背中に腕が回されていてそれ以上引けず。
「われが否を言わすと思うてか?」
にぃ、と間近で笑んだその顔は、彼が昔よく、自称悪だくみを考えているときの顔そっくりだった。
あくどい顔だけど、なぜかそれにどきりと心拍数の上がる心臓。
あれだ、これ、勝てないわ。
何を基準に勝つとか負けるとか、そういう判定物じゃないんだけれど、勝てないわ。
「ヒヒヒッ、赤い赤い、愛いなァ、われはぬしが愛いぞ?」
「くぅううう、今、こいつちょろいとか思っただろ!絶対思っただろ!」
余裕綽々で掌の上を転がされている。
悔しいけど、嬉しい。のが、やはり悔しい。
|
|
|
心地よい日差しの日だった。気候も安定しており、体の調子も良い。執務も軍略も一区切りを終えたところでいつものように何の前触れもなくあやかしが顔を出した。
毎度われを見たところで「あ、今日倒れてないね」と言いやるが、こやつはわれのことをなんだと思っていやるのか。…まぁ、こやつが姿を現す時の何度かに一度は寝込んでいるのだが。
「ぬしは物を食いやるのか?」
茶を飲み、菓子に手を伸ばし、ふと疑問に思っていたことを訪ねた。
こやつが物を食している姿を見たことがない。いや、あやかしとはそもそも何かを食すのだろうか。物か?人か?食欲自体あるかどうかも怪しい。
しばし考えるしぐさを見せていたそれは、
「食べる必要がない、かな」
と、言葉を伝えてきた。
「ふむ、食欲がないと」
「いや、それはあるけど」
食欲はあるが、食べる必要がない。
なるほど、三成がそのような体質であればこちらとてあれこれ世話焼く必要もないというに、まことあやかしとは摩訶不思議な体質よ。しかし、必要がない、というのはすなわち食べられはする、ということ。
「なれば、ほれ」
すいっと羊羹をあやかしの口にも運べる程度の形に切り、差し出した。
不思議そうに羊羹を見つめるあやかし。
あやかしの世界には羊羹がないのであろうか、それとも。
「やれ、」
この毒蛾の手からはさすがのあやかしも食えぬか?と、皮肉を飛ばそうとしたところでぱくりと小さい口が羊羹をさらった。
食いよったわ。
味を確かめるように咀嚼し、飲み込み、首を傾げた。
「食べた気がしない」
「……ヒヒッ、さようか」
人は皆、われを忌避する。今の仕草を他の者にすれば、まぁ立場もあろうが恐怖を顔に貼り付け死にそうな顔で食うか、お許しを、と希うか。だというに、このあやかしときたら。
「何、嫌いなの、羊羹?」
「いや?」
頓珍漢な答えを返すあやかしに笑みさえ浮かぶ。
それをどうとったか、ふぅん、と返答とも取れぬ声を返し、ごろり、と日差しの当たる板間に寝転がった。
あやかしは日の光を厭うかと思っていたが、こやつの場合はそうでないらしい。
残りの羊羹を口に運ぶ。
甘い餡子が口の中で蕩けた。
羊羹はさして好きでも嫌いでもなかったが…、これは特別旨い。
いつの間にやらあやかしは消え去っていたが、この日以降、われの茶請けは羊羹と相成ったことを、きっとこのあやかしは知らぬであろう。
※バックブラウザ推奨
+++あとがき+++
自分の手から物を食べてくれたのが嬉しくて、以降羊羹が好物になってしまった大谷さんでした。
ちなみに石田先生は見舞いに行ってもちらちら時計を気にする吉継さんに、今日アレは来たのかと聞いたところ、いや、まだよ、と返ってきたのを聞いた瞬間鬼電を始めました。
春休みなのだからアレにも予定があろ、と呆れたけれど止めない吉継さん。
毎日顔を出してほしい、実は大人げないけど見栄っ張りだからそんなことおくびにも出さない吉継さん、萌え。
2014.02.03