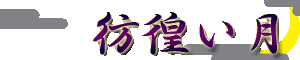手と手、目と目
披露宴の際に配られる式次第に添えられた自己紹介。
名前、出身、生年月日、心に残る思い出、相手の好きなところ、直してほしいところ、どんな家庭を築きたいか、といったありきたりなものだ。
「これさ、お互い秘密にしておかない?」
「ヒヒッ、後でのお楽しみ、か、良い策よ」
ということで私は当日まで彼のソレを見ることはなかった。
式が終わっていろいろ片付けた後でようやくのんびりできた日。
「ねぇ、吉継さんて、私の手が好きだったの?」
お茶に羊羹、といった純和風のお菓子を食べながらようやく聞きたかったことを聞けた。
この男、いつも言い回しが面倒くさくて日本語をしゃべらないくせに、好きなところ、の欄には“手”と一言どころか一文字で済ませてきたのだ。これは気にならない方がおかしい。
手、何かあっただろうか、と思うも、別段特別な思い出があるわけでもない。
吉継さんはそんなもの決まっているだろう、と言いたげな目を向けてくるが、わからないから聞いてるんだからね?
「昔、われはよう寝込んでおったろ」
「ああ、うんそうね、よく看病しに行ったね」
「初めて看病したときを覚えていやるか?」
初めて看病したとき。
それはいつのことだったろうか。たぶん、おそらく、高校一年生頃ではあるのだが。
「……いや別に?」
「さすがよ、期待を裏切らぬ物忘れぶり、もはや感嘆の域よなァ」
「はいはい、ごめんね」
直してほしいところ、の欄に物忘れ、と書かれてしまったので何とも言えない。
前世の分まで記憶持ってるあんたの記憶力と比べないでほしい。
いや、単に頭の出来の違いなんだろうけれども。
「ぬしがな、ひと肌恋しいのか?と言いながらわれの手を握ったのよ。
しかも、その次の日には熱が引いた」
いや、そんな馬鹿な。それどんな神様だよ。
言葉に出さずに呆れた顔を作れば、吉継さんは例のヒヒッとひきつった笑いをした。
「まぁ、そう変な顔をするな。
われもまぁ気のせいとは思ったのだが、ぬしが看病するたび、触れるたびに、われを癒すのよ、体も、…心も、な。
ゆえにの好いているところと聞かれれば一番に手が出てきたまでのこと」
湯呑から離れた彼の手を取る。
握った手を、緩く握り返されて、なんだかとっても愛しい気持ちにさせる吉継さんはさすがだった。
「知っておるか?今生でもな、ぬしと会い見えたその時から皮膚の治療も、歩行のリハビリもうまいようにことが進みやるのよ」
「いや、それは知らんかったけれども、私にそんな力ないよ」
「ヒヒッ、われ専用よ」
言っておくが、ほんっとうに私にそんな変な力はない。
ていうかあったらなんかこう、もっと売り込みかけてるっていうか一般企業じゃなくて医療関係に従事できるんじゃないだろうか。
「して、ぬしはわれの瞳、であったか?
このような気味の悪い目を好いているとはぬしも物好きよな」
あっかんべーの要領で、目をこちらへ向ける吉継さん。
この男、年甲斐もなくそういうガキっぽいしぐさをするのは狙っているんだろうか、可愛いくそう。
「瞳、なんだけど、まぁ、うーん、なんというか、吉継さんの視力?」
「われは両目ともに裸眼は0.1を下回るが」
「いや、そうじゃなくてっていうかコンタクトかよびっくりだよ」
私よりも早く起きるし、私よりも遅く寝るから気付かなかった。
流し台の周りもそれらしき備品はないんだけどなぜこの人コンタクトしてることを巧妙に隠したのかと…!
私の変顔が気に入ったのか、またも引き笑いをする吉継さん。
だめだ話がそれる。
「えっと、話がそれたけど…昔も今もさ、吉継さん、私のことすぐ見つけてくれるから」
いつに現れようと、どこに現れようと、姿を消していても、人ごみの中でも、私が見失ったときでも。
吉継さんは不思議とすぐに私を見つける。今生になってからは見つけた後必ず、私の右手をその左手でさらうのだ。
それが嬉しいし、幸せだし、安心して私は歩いて行ける。どれだけ迷子になってもきっと彼が見つけてくれるから。傍に、いてくれるから。
「だからね、吉継さんの瞳が好き」
えへへ、と間抜けに笑えば、柔らかく手を引かれて胸の中にいざなわれる。
「ぬしはまっこと、心の臓に悪い、萌え死ぬわ」
きゅう、と抱き締める手は優しくて、安心して身をゆだねる。
引っ付き虫の吉継さんはよくよく私を抱き締める。
本当は、直してほしいところに場をわきまえずに抱きしめること、と入れたかったんだけれど、書いた後でこれただののろけだヤベエやめよう、となったのだ。
それに、なんだかんだと慣らされてしまって嫌でもない。
結局直してほしいところは空欄のまま。
「直してほしいところはほんにないのか?」
まるで思考が読み取られる感覚にも慣れた。
「んー、考えとく」
「さようか」
そのあとは、沈黙。
築きたい家庭は、不思議と一致していて、思わず披露宴の中で顔を見合わせて笑ってしまったものだ。
二人、身を寄せて、段々とあったかくなる。
これは二人してお昼寝コースだな、と、やってくる微睡に身を任せて、ゆっくり瞳を閉じた。
+++あとがき+++
新婚生活なう。リア充末永く幸せになるとよいのです。
※バックブラウザ推奨
2014.03.09