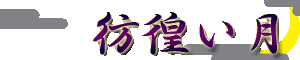カップケーキ
図書室の窓から仲睦まじく帰っていく二人組を眺める。
男子が長い足を颯爽と動かし先を行き、女子がそれを小走りで追いかけている。
一般的には仲睦まじいようには見えないけれど、それが彼らの距離だと知っている私からしたら、仲睦まじいのだ。女子は決して男子を見失わずについていくし、男子は一定間隔でついてきている女子が止まれば止まるだろう。そしてきっと、何をしている私から離れるな、と、怒鳴り声とともに目尻を染めて腕でもひっつかむんじゃないだろうか。
容易に想像できて音もない笑みがこぼれた。
「ひとりでにやにやと、ぬしは不審者か」
「あだっ」
ごん、と、ハードカバーの角が頭に打ち込まれ、痛みで机に突っ伏した。
「痛い」
恨みがましく犯人を見上げれば、そいつはどこ吹く風とばかりに私を殴ったハードカバーの本を広げてすでに読書の体勢だ。
やれやれ、と文句を引っ込めてまた窓の外を見る。
もうあの二人は校門を出て、すでに豆のように小さくなってしまった。
夕暮れの空。
しばらくしたら太陽は水平線の向こう側に隠れて、橙が段々と藍に変わるだろう。
暖色から寒色へ変わっていく様が、私は好きだ。
図書委員が閉室のお知らせを告げる声に、ようやく窓から目を離して、カバンを持って立ち上がった。
「か弱い病人のわれを置いてゆく気か?」
「元気な病人じゃなくて?」
持病が云々、聞いているけれど、そんなのお構いなしに元気な病人である刑部のカバンもついでに持つ。
「ん」
「はいはい」
分厚いハードカバーの本をずいっと差し出される。
私はあんたのパシリじゃないんですけどねー。
と、思うけれど口にはせずに彼のカバンの中へとしまう。
「ほんに物好きよな」
ぼそりと呟いた彼の言葉に苦笑する。
何に対しての評価なのか、はなんとなくわかる。
自分のような気味の悪い人間の相手をよくする気になるな、と大体そんな意味だろう。
彼――刑部とは幼馴染というわけでもなければクラスが一緒でもないし、そもそも学年だって違う。共通点といえば、お互い部活に入っていないことと、放課後図書室での遭遇率が以上に高い、という二点ほど。ついでに言うと名前も知らない。たまたま私のクラスメイトであり、先ほど豆のように小さくなっていった二人組経由で“刑部”と呼ばれていたから私もそう呼んでいる。
「お互い様だと思うけど」
無口で無表情で、友達と呼べる友達も少なくて、何を考えているのかわからないと定評のある私と仲良く下校なんてする気が起きるんだから、刑部も大概である。
私の答えに、然様か、と呆れた声で答えて、ゆっくりと杖を突きながら彼は歩き出す。
その彼に並ぶようにして歩くのが最近の私の下校スタイルだ。
帰り道に何を話すわけでもない、思いついたときのそういえばこんなことが、と適当なことを話題に出す。それが盛り上がるときもあれば盛り上がらない時もある。でも盛り上がらなかったとしても別段気を悪くするわけでもなく自然体。
「鞄が開いておるぞ、ぬしはほんに隙だらけよな」
ひひ、と喉で笑う彼の手には私の財布が。
いつの間に。
歩みの遅い彼から財布を奪い返すことなど造作もないと思いきや、最低限の動きでひょいひょい、と避ける。
「ちょっとー」
高校生のお財布事情なんてたかが知れているだろうに。
実際野口さんが一枚程度しかない。
数度手を伸ばして返す気が全くない様子に息をついた。
諦めた私の様子に刑部はヒヒヒッ、と笑い声をあげた。
鞄を開けていたのがいけないのだ、と鞄を締めようとしたら中にやや潰れたカップケーキが入っていた。
家庭科の授業で作ったものだが、どうやって石田君に渡せばいいかな、と相談に乗っているとき適当にうなずきながら帰り支度をしていたせいだろう。入れたことすらすっかり忘れていた。
「やれ、中身がしょっぱいな」
「お小遣い、月に千円なんだからやめてくれる?」
「なぁに駅前の和菓子屋で一服くらいいけよう」
「おい」
それは私の財布の中身でか。しかし返す様子を一切見せない。性質が悪い。
「刑部って甘いの好きだっけ?」
そんなイメージないんだけれど。
にぃ、と私を見ながら笑んだ。
「今日はそんな気分ゆえ」
私の財布の中身を減らしたいがための言い訳にしか聞こえない。
鞄の中のカップケーキを取り出して、刑部に押し付ける。
「ほら、甘いもの!」
片手に杖、片手に私の財布。杖は必須、となれば受け取るには財布を私に返すしかない。よし、私にしては珍しく知的。
刑部は私の差し出すカップケーキに顔を寄せてじろじろと見たあとに、私を見る。
「…ぬしが作ったのか」
「じゃなかったら持ってないでしょ」
ふむ、と一つ頷くと、彼はなんと私の財布を放り投げた。
「ちょ!?」
私の視線は財布を追うが、刑部はその隙にさっとカップケーキの包みを奪った。おかげで空になった両手で何とか財布をキャッチする。
「おお、見事ミゴト」
「見事じゃないよ…」
今度こそ、と財布を鞄にしまい、きっちりとファスナーを締めた。刑部はよほど甘いものを食べたかったのか、カップケーキの包みをさっそくと開けて包帯の隙間から口へと運んでいる。
「立ち食いなんて行儀悪いよ、刑部」
「駅前の立ち食い蕎麦屋の目の前で同じ言葉を吐いて見せ」
「むぐ」
そんな世の中の戦うお父さんたちに喧嘩を売れるわけがないじゃないか。ああもう口じゃ勝てない。
結局言い返すのはやめてため息をついた。
「うむ、甘い」
やがて完食した刑部の口からいやに上機嫌な感想が耳に届いた。こんなに機嫌がいいのは、珍しい。
「包帯に、食べかすついてるよ」
「む」
「そっちじゃなくてこっち」
食べかすの反対側に手を伸ばした刑部に呆れながら、食べかすを取ってあげた。そのまま口に運んでみるも、やはり普通の味だ。
「……はぁ」
馬鹿にされたようなため息をつかれて首を傾げた。別に頬に直接ついた食べかすだったわけでもあるまいに。
何でもない、と歩き出した刑部に並んで歩く。
「…まぁ、気に入ったなら次の実習のもあげるよ」
「ほぅ、われに貢ぐか、いや感心よ」
「だって、自分で作って自分で食べるの微妙でしょ?
いらないなら、」
「いらぬとは言っておらぬ」
特別あげる誰かがいるわけでもないので、機会があればまたあげる旨を伝えれば、やや被せ気味に返ってきた。
そんなにおいしかったかなぁ。出来立てを実習時間に食べたときも、こんなもんか、くらいだったんだけど。
ぱちくりと瞬きをして刑部を見ていれば、なぜか杖で足を殴られた。
「なんで殴るの…!」
「む?何か言ったか?」
聞こえないふりをされた…!
「……じゃあもうなんか作ってもあげない」
悔しいのでむすっとしながら言ってやれば、一瞬だけ刑部が止まって、じろり、とこちらを見た。やや睨み気味で怖いものの、屈して堪るか、と睨み返す。
「……一度口から出した言の葉を覆すか。
まぁよい、新聞部の人間に面白おかしい垂れ込みをするなどわれには造作もないこと。
たとえば、そうよなぁ、ぬしが用務員に懸想をしているらしい、あたりが愉快か」
げ。
用務員の黒田さんといえば、不運が代名詞でむさくるしいことこの上ない人。
ただでさえ友達が少ないし暗いせいか、かげでこっそろ指さされているのを知っている。それが悪化するのは避けたい。
「性格悪い!黒田さん相手とかやめてよ」
「ならば先の言葉を撤回することよ」
「わかったわかった、なんか作ったらちゃんと刑部にあげるから」
私の必死の様子に、ようやく機嫌を直したのか、いつもの引きつり笑いで刑部は答えた。
彼を相手にうまく立ち回ろうだなんて、無理なのかもしれない。
かといって、やられっぱなしも…なんだか悔しい。
今度の家庭か実習の折には、くっそまずいものでも作ってやる。
決意の直後、
「よ。
先の言葉、違えればぬしにさんざめく不幸を見舞ってやろ。
きちりと美味なものを作りやれ?」
口元は笑いながらもやたらと真剣な目で告げてきた刑部には、私の考えはお見通しなのかもしれない。刑部、恐ろしい子…!
+++あとがき+++
鞄にカップケーキが入っていたのは当然気付いていてヒロインさんの手からカップケーキもらうために嫌がらせ(趣味)込みで色々頑張る大谷さん。
※バックブラウザ推奨
2014.06.01