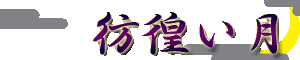人間不信の彼女と彼
成績優秀、愛想が良くて気配りができて。
高校生だっていうのにこんな子がいるなんてさぞかし親御さんは自慢だろうと思ったのだけれど、少し話してみて分かった。
物凄く人間不信を拗らせている。偏執病とも言えるくらいに。
成績優秀なのは隙を見せないため。
愛想がいいのは相手に不快感を与えず自己を防衛するため。
気配りはすべて自分をよく見せるため、味方づくりのための根回し。
毎日周りを警戒して誰一人として信用せず、常に一歩線を引く。
思わず家族構成を調べてみたものの、両親ともに健在、三人兄弟の真ん中、経済状況も悪いわけではなくいたって普通。
どんな育て方をしたらこうも人間不信を拗らせられるんだろうか。
そんな彼女が、恋人(?)を作った。
相手は同じような人間不信の後輩だ。
「先輩、今日は冷えまする。これを」
「あ、ポタージュ。ありがとうね、吉継君」
「ヒヒッ、礼には及びませぬ」
はたから見れば流行のリア充とやらであるが。
しかし、この光景にうすら寒さを感じているのは僕だけではない。
生徒会の活動中とはいえ、同席してしまった官兵衛君が青い顔をしていることがいい証拠だ。
彼らの性根を知っているこちら側からしたら今の会話はこうだ。
「先輩、今日は冷えまする。これを」→(いい加減われに絆されてはいかがか?)
「あ、ポタージュ。ありがとうね、吉継君」→(ポタージュくらいで絆されるわけがないでしょう?)
「ヒヒッ、礼には及びませぬ」→(やれ、相変わらずなお方よ、愉快ユカイ)
……いったい何の遊びをしているんだい、君たちは。
声を大にして言いたいけれど、彼らが口に出していない以上、部外者から口を出すのは藪蛇だろう。
「…君たちは本当に面白いね」
「あら、それはありがとう」
にこり、と彼女は嬉しいと言う感情を少しもにじませない顔で笑った。
その笑顔に官兵衛君が、ケッと空気を吐き捨て、直後に大谷君から筆箱が飛んだ。弾丸ライナーのようなそれは見事に彼の眉間に当たる。
まぁお互いが楽しいなら止めはしない。どちらも僕にとっては良い仲間であることに変わりないのだから。
そんな彼女がじっと大谷君を見つめている。
「何か?」
「可愛いな、と思って」
「おい、お前さん目と頭は大丈夫か」
「吉継君のマグ」
「へ?」
「ちょうちょ、可愛いな」
脱力する官兵衛君とそれをケタケタにやにや笑う二人に、おや、と思う。
途中までは明らかに官兵衛君を乗せてからかうための言葉だっただろう。
けれど。
「ちょうちょ、可愛いな」
その言葉に少しばかり乗せられた感情。
偏執病の嫌いがある彼女は自分が感情を乗せたことに気付いただろうか。
偏執病の嫌いがある彼は、向けられた感情に気付いただろうか。
まぁ…、どちらでも構わないか。
「楽しく遊ぶのは結構だけれど、仕事を終わらせてからで頼むよ」
結局僕が抱える想いは変わらない。
偏執病だろうがそうでなかろうが、それが直ろうが直るまいが、…この二人が上手くいけばそれでいい。
そのために奔走するつもりはさらさらないけど、見守るくらい苦にならない。
彼らの返事と官兵衛君のお決まり文句を耳にしながら、紙面に目を落とした。
+++あとがき+++
副会長目線でお送りしました。常に心理戦のパラノイアカップル、結構気に入ってます。
※バックブラウザ推奨
2014.07.02