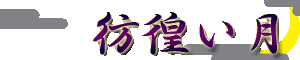雷に打たれたように
空は曇天、豪雨が大阪を打ち付け、雷鳴が轟く。
その女は一人、縁側で空を仰いでいた。
再度、空がきらめく。その少し後に、轟音。
光る間際、僅かに見えた口元が弧を描いていた。
物好きな。
頭に浮かんだ言葉を口には出さなかった。
「やれ、雨乞いか」
尋ねれば、ゆるりと緩慢な動作で女――はこちらを見た。
自称未来人。未だ来らぬ世を知る者。
どう媚びを売ったかは知らぬが、賢人が手元に置いた稀人であり、われを恐れることなく真っ直ぐと捉える稀有な女。
「刑部さんはいつも唐突だなァ」
ふにゃり、と形容しがたい様子で相貌を崩す。
どこか左近に似た口振りをする。いや、あれほど軽くはないが。
油断させようとしておるのか否か。
気配はダダ漏れで突飛もないことばかりを口にし、間抜けっぷりをようよう披露してくるだが、最近はその危なっかしさゆえか三成までもが世話を焼く始末だ。
「それは申し訳ないことをしたなァ、稀人よ」
言葉だけ口から出せば、あ、今絶対申し訳ないと思ってないでしょ、などと呆れた顔をされた。
そのとき。
「あ、また」
稲光が走り、曇天へと視線を戻す。しばししたのち、ごろごろと雷鳴が轟くのを愉快だとばかりに口元を緩める。
何がそんなに面白いのか。
「梅雨が明けるねぇ」
雷が鳴ると梅雨が明ける。
そんな話を聞いたことがあった。
しかし、梅雨が明けるのを喜ぶ、というよりも、雷自体を面白がっているように見える。
「…恐ろしくは感じぬか」
時として天罰のように人に落ち、命を奪う雷に。
神鳴りとも呼ばれ、民衆に恐れられるそれに。
嬉々として天を仰ぐ女は…腑に落ちぬものがある。
雷鳴に、恐れ戦き、悲鳴でも上げて震えて居れば可愛らしいものを。
「綺麗じゃない?」
こちらの考えが分かるのか、否か。
笑って、稲光の直後、光る空を見上げながら数を数え始めた。
ひとつ、ふたつ、みっつ。
いつつ、を数えた地点で雷鳴。
「五つかぁ、三百四十をかけて、一点七キロってとこか。
今の音、どっかに落ちたね」
火事になってないといいけど、などとぼやく。
口ぶりからして、前半は何かの算段。
おそらくは天罰の下った位置。
これが未だ来らぬ世の知識、とやらか。
「なるほど、天罰を下すまじないか、恐ろしや…」
「ちがっ、そういうオカルティックなもんじゃないってば」
おかるてぃっく。また面妖な言葉を。
左近のような軽い口調と訳の分からぬ言葉を混ぜてくるのだから余計に訳が分からない。
包帯の奥で眉をひそめるわれを放り、はたとえば、と言葉を続ける。
「花火、てこっちもあるよね。光るのと、音が鳴るのと、ずれるでしょ?雷もそれと一緒。光ってから数え始めた秒数と、三百四十メートル、をかけるんだけど……しまった、私こっちの距離の単位わかんないや」
あれほど夢中だった空から目を離し、畳がどうの、尺がどうの、ああでもない、こうでもないと一人ぶつぶつ言い始める。
こちらとあちらと、単位が違う。
単位とは、物事の基準、認識、常識。
なるほど。
どこか納得した。
それらが違えば、これとわれが違うのもまた道理。
われの知るヒトであってヒトでない、その辺りにのさばるヒトとは別物。
そう考えれば違和感がない方がおかしいのだ。
すとん、と、女にまとわりつく違和感を許容できた。
うんうん唸り始めた女から目を離し、先ほどがしていたように天を仰ぎ見る。
日常肌を焼くような忌々しい太陽は身をひそめ、厚くどす黒い灰色が空を覆う。
しかし、そこから落ちる雨粒は段々と勢いをなくしていった。
「おお、ぬしのまじないで雨が引きよったわ」
「だ、だからまじないじゃないってば!」
それから、またも空を見上げ、あー、上がっちゃったか、とぼやく。
「いやはや、さすがは稀人よ」
「だー、かー、らー!」
からかうように続ければ、両手を上げて抗議をしてくる。
そのような小さな抵抗でわれに勝てると思っておるのか。
それにしても。
こやつ、先ほどからわれの言葉を真に受けすぎではないか?
ヒ、と引きつった笑声が口から洩れる。
「やれ、おかしやおかし。
はほんに可笑しなおなごよなァ」
「全ッ然、普通の、一般人、なんだってば!」
むっすぅ、と音がつきそうなくらいに口を尖らせる女にまた一つ笑えば、あれ、と妙な声を出して次に首を傾げた。
忙しない女だ。
「刑部さん、今、私の名前…」
言われて、はたと気付く。
確かに、いつも稀人稀人と呼んでいたので名を呼ぶのは初めてだ。
そのことに、特に意味など、そう、意味などない。
じっと喜色を込めた黒々とした瞳をこちらへ向けるにざわりと胸の奥で何かが動く。
何と位置づけるべき感情か惑い、一呼吸分止まった。
胃が、腸が、臓物が、浮くような、奇妙な感覚。
これは、――不愉快、そう不愉快だ、じろりと他者には畏怖される色素の反転した瞳でねめつける。
「、ほう、われは人の名も覚えられぬ阿呆と思われていたのか、やれ、心外よ」
「ちがっ、なんで刑部さんはそうネガティブな受け取り方しかできないの…」
ふむ、今の言葉なら文脈からわかる。暗い、やら、後ろ向き、やらその程度だろう。今更よな。
われの睨みに臆することなく脱力し、文字通り肩を落とす女がまた可笑しくて一つ笑う。
喜色よりもむくれ顔が似合いよ。
溜飲を下した気分だ。さて、そろと戻るか、と輿を浮かせる。
――と、刑部さん、柔らかい声が輿の動きを止めた。
「これからも、名前呼んでよ」
そっちのほうが嬉しいから、と。
微笑みを浮かべて見上げてくる。
先ほど去ったはずのざわりとした、――不愉快が帰ってくる。
どうするべきか、どうすれば、この不愉快が去るのか。
この顔がいけない。
われを臆することなく見上げ、微笑むこの顔が。
くるり、止めていた輿の方向を変え、視界からの顔を外した。
「刑部さん?」
不思議そうな声に、心の臓が僅かに跳ねる。
気味が、悪い。
ふわふわと浮ついた臓物の感覚が、どうにも腰を据えかねる。
「ふむ、急に耳が遠くなったわ、やれ、困ったコマッタぁ」
「小学生のいじめか…!!」
結局はそんなことを口にして、逃げるように、だがそれと悟られぬようにゆるり輿を進めた。
初夏の、雨上りの湿気が籠ったか、些か暑い。
雨の縁側に寄って熱でも出したか、否、そこまで軟ではない、はずだ。
懐から扇子を取り出し開く。
パタリパタリ。
風が、ぬるい。
それでも、暑さが去るように、あの気味の悪い落ち着かなさを払うように、パタリパタリ、扇子を動かした。
+++あとがき+++
恋しちゃったんだたぶん気付いてないでしょー。
の大谷さんでした。最近雷がうるさかったので、つい。
※バックブラウザ推奨
2014.07.08