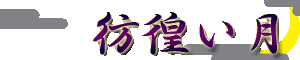後輩からの歪んだ恋慕
他人に期待はしていない。
いや、言い方が正確ではない。
期待をしているが、期待をしたところで無駄だと知っているので、期待しないふりをしている、が正しい。
期待をしないことを、望まずにいることをできない私は、相当な馬鹿なのだろう。
だから私は盛大に、相手に受け取りやすいように、計画まで練って善意を押し付ける。
情けは人の為ならず。
中学を過ぎたあたりから、半ばそれは癖となっていた。
そうして、やはり、と思う。所詮、人間なんて自分に良くしてくれる人間に対して尻尾を振る大層浅ましい生き物なのだ、と。
「先輩は、大層都合の良き女よなァ」
一つ下の車椅子を乗りこなす包帯まみれの後輩に、ワインレッドでチェック柄のブランケットを贈ったら、なんと暴言を吐かれた。
「あらやだそんなこと、」
この後輩――大谷吉継は頭が切れる人間だった。回転数なら倍近い勢いで抜かれているだろう。生徒会の後輩ということを名目に構って構って構い倒して、毒のある暴言を笑いながらやり取りする間柄になったのはいつのことだったか。
「ない、と申されるか」
私と彼の会話を聞いた人間はこぞって、怖い、黒い、流石、などなど言うわけだが、いったい何の取り柄もなく平々凡々の私をどんな目で見ていることやら。それなら現副会長のアレほどじゃない、と苦笑をすれば、いや匹敵する、などと過大評価が帰ってくるのは善意の押し売りの成果か否か。
「ううん、今更、でしょ」
私って都合のいい女なのよ、重宝しなさい、と笑ってやれば、一瞬目を丸くして、ヒヒッと笑った。
「われだけの都合の良き女になる気はありませぬか、先輩?」
同じようなセリフを高校に入ってから何度聞いたことか。
「そうねぇ、私の期待を大きく超えられる男になれたら考えてあげるわ、後輩」
誰かの特別になんてなる気はさらさらない。そんなものは私の中で意味がない。
誰の特別になったところで、一番は絶対に自分になるのが人間だもの。煙に巻いて相手が諦めるのを待つだけだ。
こぞって顔が整っていたり、優秀な人間の彼女になりたい、なんて騒ぎ立てるクラスの女子たちのなんて可愛らしいこと。恋に恋して、あばたもえくぼ、盲目なことが愚かしくも愛おしい、なんて口から出したらどんな目を向けられることやら。
恋い慕い、愛でるも慈しむも、すべて偽善で、すべて自己満足だと彼女たちは分かっているのだろうか、私には関係ないが。
「では早速」
普段そうやる気にならない後輩が、珍しくやる気を起こしたらしい。
私を専用の都合のいい女にしたい、というドエス極まりない出発点だが。
「お誕生日、おめでとうございまする、先輩」
私の前に手のひら大の箱がぽすんと着地した。
おおぅ、これはなかなか予想外。
確かに今日は私の誕生日で、日々私から善意を押し付けられている面々からお祝いの言葉やらお祝いの品やらを贈られたけれども。記憶を辿れどこの後輩に誕生日など教えたことはなかった。
「やだ、大谷君ストーカー?」
「人のことは言えますまい?」
ヒヒヒ、と気味の悪い引き笑いをする後輩君は、どうやら私が善意の押し付けをするために生徒会の権限を使って生徒名簿からみんなの誕生日を洗い出したことを知っているらしい。あらまぁ、誰に似たのか悪い子だこと。
ころころと掌で箱を転がして、その場で開けてみる。
中から出てきたのは私が好きな動物を模した携帯ストラップ。しかもとっても私好み。
「かわいい〜、やるねぇ、大谷君。さすが頭いいだけあるよ」
さっそくと携帯にぶらさげていたストラップを交換する。
ネックレスやブレスレットなどを贈ってくれる人もいたけれど、学校での装飾物の着用は禁止されている。もちろんこっそりつけてくる女子もいるにはいるが、私は面倒だからつけない。休みにつける前提として渡すならば、その後に遊びに誘う文句でも来るかと思いきや、贈っただけで満足する人が大半で、まぁそんなもんだよね、と失礼ながら上から目線で思ってしまったことが何度かあるわけだ。
そういうところを大谷君はしっかり観察していたのだろう。まぁ副会長さんとアクセ渡すならこれくらいまでしないとねぇ、みたいな話を生徒会室でしていたせいかもしれないが。君は本当に面倒くさい女だね、と褒め言葉を貰った記憶もある。
「まァ、この程度で先輩を落とせると思うてはおりませぬが。
先輩こそ、目の前で開けて喜ぶ姿を見せ、褒め言葉と共にさっそくと携帯に付けるとは流石、男心を日々弄ぶだけはありますなァ」
「人聞き悪いなァ」
少し好意的な行動をしただけで舞い上がる方が悪い、と皆まで言わずとも賢い賢い後輩ならわかっているだろう。
「ヒ、ヒッ、ほんに恐ろしいお方よ」
「ふふ、それはどうも」
きっとその内、大谷君も面倒くさくなって諦めるだろう。
他人に期待するだけ無駄なのだ。
「われは、」
「ん?」
ぐるりと彼が私の前に回り込む。
彼の変わった色素の瞳が弧を描いて楽しげに私を映す。
口元はよく見えないが、それも弧を描いているのだろうと想像できるほど、彼は楽し気に口を開く。
「先輩のヒトへの絶望しきったこの目の色を大層気に入っておるのです」
これは…、彼流の告白のつもりなんだろうか。
もしかして物凄く、面倒な惚れられ方をされたのではないだろうか。
読まれた、気付かれた、とかそういう次元ではなく、そこ気に入るの、と私はあきれる表情を隠しもせずにして、それを見た大谷君がまた満足そうに喉を鳴らす。
エスなのか、エムなのか、際どいラインだなぁ。
まぁでも、
「面と向かってソレ言ってきたのは三人目だけど、気に入ったって言うのは大谷君が初めてだよ」
面白いね、と、胸糞悪ぃ、と正反対の感想だったのは記憶に新しい。
大谷君とのブラックジョークの投げ合いは楽しいから、彼が根負けするまで楽しむのも、悪くないかもしれない。
それはそれは、と喉を鳴らす彼と同じく、私もくすっと笑うのだった。
+++あとがき+++
敬語の大谷さんを書きたかったんです。歪みねぇ歪んだ大谷さん大好き。
その内主人公さんが無意識で大谷さんにだけ期待するようになって、大谷さんが一人勝ちすればいいと思います。
※バックブラウザ推奨
2013.12.28