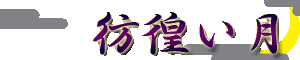白いハンカチ
何だか色々と疲れていたから。
というのがその時の心情として一番当てはまるけれど、理由とかは全然考えていたわけではなくて、ただなんとなく、足が向かっただけだ。
普段踏み入れないそこは、意外とあっさりと開いた。
先生が鍵をかけ忘れたのか、はたまた壊れているのか誰かが壊したのか。
そんなこともどうでもよくて、私はこの日、はじめて屋上に出た。
風薫る、なんて言うのは五月の季語だけれど、五月でない今でも充分に風は薫って、よく分からない解放感のようなものを私にくれた。
静かに息を吸って、吐く。
ああ、いい天気。
珍しく部活をサボって、珍しくこんなところに来て、何がしたかったのか自分自身さっぱり分からない。
でもこの、何も遮らない清々しい青い空を見ただけで鬱憤やら、なんやら吹き飛んでしまったような気がした。太陽の力って偉大だ。
屋上に足を下ろしてグランド側と反対の方向へ歩く。もし部活をサボっていたなんてバレたらこってり絞られてしまう。
一応真面目で通っているらしいので、それを裏切ってしまっては申し訳がない。と、いうのは言い訳だと分かっている。
卑怯な私。
口を開くのも億劫で、心の中で呟く。
ちょうど日が当たるようになっているドアの裏側まで来て座り込む。
「進歩ないなー……」
昔から、そうだ。
何かあると人に当たって、どうしようもなくなったら一人きりで自分の内にこもって解決しようとする。
実際、解決、なんてした試しはなくて私が勝手にこじつけた理屈で自身を納得させてるだけ。
誰かにわかってほしいけど、他人のことが分かるほど人って上手く出来ていないものなんだ。
誰かにそばにいてほしいとも思うけど、他人から見たら自己解決の過程なんて全然面白くないだろうし、他人に頼るスタンスを取りたくないと仰る私のプライドさんが胸の内におわすのだ。
非常に迷惑極まりない。
単純なようで複雑で、筋が通っているようで支離滅裂。
そんな自分は心底嫌いだ。
……まあ好きなときもあるが、そういう無駄にプライドが高いところや自身を信じきれない弱いところが、嫌いだ。
「……はぁーー……」
糸のような息を吐く。
細く長くゆっくりと。
それは私の中で凝り固まった何かをほぐして溶かして大概に追い払うかのよう。
ため息をつくと幸せが逃げると言う人がいるが、私は心を穏やかにするための儀式なんだと思う。
儀式は、言い過ぎか。
もう一度ため息を吐き出して、私は目を閉じた。
床から伝わる寒さに身を震わせて起きる。
ここはどこだっけ。
などと頭を働かせていたその時だった。
「おはよ」
隣から、男の声が、した。
勢い振り向けば、吹き出すワイシャツ姿の男と、ばさりと私の肩から落ちる何か。
急いで何かを目で追えば、それは黒くて、学ランだと分かった。けれど混乱は収まらなくて、
「な、ぇ、え……?」
などと意味不明な声が口から漏れている。
クックと笑いを漏らす目の前の男に見覚えはない。
ざっと目を走らせた。
明るい色の髪、をヘアバンドでオールバックにしていて、目立つ容姿だけど、やはり見覚えはない。
分かったのは上履きの色が私と同じということだけだった。
「よく寝てたねー。いつ学ランに涎足らされるか、俺様ドッキドキだったぜ」
よ、涎!?
言われてあわてて口許をぬぐう、が、涎どころか何の液体も垂れていない。
か、からかわれた?
かぁっと熱くなる顔を見られたくなくてうつむいた。
と、学ランが目に入る。
「これ……あなたの、ですか?」
「そ」
「ありがとう、ございました」
返すと、どーいたしまして、と軽い返事が帰ってくる。
ふと見上げると、茜色。
立ち上がって制服についた埃を払う。
何時なんだろう。
時計はする主義じゃないし、携帯を鞄から出すのは面倒だった。
寝起きのせいかふらふらともつれる足取りで歩く。
「ちょっと。何してんの」
柵に近づけば、後ろから腕を引かれた。
捕まれた腕から手を追って、相手の腕、方、顔まで顔を向ける。
そこにはさっきまで私に学ランを貸していてくれた人で、その表情はなんとも言いがたそうなもので、……もしかして、自殺するとでも勘違いされたんだろうか。
「夕焼け、見ようとしただけですけど」
言えば、脱力された。
「ったく、紛らわしい……」
「それは、すみません」
苦笑して私は柵に手をかける。
いつもなら部活で見れない夕焼けはとても綺麗だった。
部活、か。
サボってしまった罪悪感がひしひしと胸に忍び寄る。
重苦しい心を軽くするため、ため息をそっと吐き出した。
空はオレンジが、段々と藍に変わっていく。
寝る前より出てきた雲も綺麗に見える。
一日で完結する世界なら、昼と夜の間一瞬だけ空が見 せる夕焼けは、この世の終わり、みたいな。
儚くて力強い光。
風前の灯?いや、なんか違うな。
ふっと息を吐いた。
帰ろう。
振り返ると、そこにはあの男がいた。
……まだ、いたんだ。
「あの、帰らないんですか?」
「ん?あ、帰る?」
「はぁ、私は帰りますけど」
「じゃ、帰ろっか」
「はい?」
「この暗い中、一人で帰る気ですかーサン?」
ぽいっと投げられたものをキャッチすれば、それは寝てたところに置いておいた私の鞄だった。
て、あれ?
「何で、名前……」
「俺様全校生徒の名前と顔、全部覚えてるから」
鼻を擦って得意顔で笑いかけてくる男。
この人、もしかして、待っててくれ、た?
「……ありがと、ございます」
「ん、どーいたしまして?」
その返事に胸が暖かくなる。
待っててくれていたと思ったらよくわからない言葉にならない何かが込み上げてきて、知らない内に溢れていた。
目から溢れる水を慌てて拭った。
と、その手をそっと止める手があった。
「あんま擦ると赤くなるぜ?」
彼の気遣いにまた涙が溢れる。
いつも、回りは違った。
私が泣くと慌てたり、よそよそしくなったり、急に優しくなったり、泣けば何とでもなると思ってるのかと罵られたり。
反応されるのが一番苦痛だった。
好きで泣いてる訳じゃない。
勝手に溢れてくるだけ。
だからそんなに構わないで。
心の中で叫んでも絶対通じないって、分かってても私はそれを口にしなかった。
だって他人からしたらただの言い訳だから。
「ありがと、ございますっ」
ただそこに誰かいてくれるという、それだけなのに、何故かひどく満たされた気持ち、だ。
「どーいたしまして」
言いながらハンカチをそっと当ててくれた。
なんて女の扱いに手慣れた人なんだろう。
擦っちゃダメだよ、と釘を刺されて、片手を繋がれたまま屋上を離れる。こいびとというより、まるで親子のようだ。
結局家のそばまで送ってもらってしまった。
「あの、クラスと名前、聞いてもいいですか?」
ハンカチ、洗って返します。
そう言うと彼はにっこり笑った。
「クラスはB組、猿飛佐助ってのが俺様の名前」
さるとびさすけ。
その名前はすっと私の中に広がった。
夜になりたての藍色に手を振って消える彼。
さるとびさすけ。
私にとって、それは特別な名前になった。
「ふふっ」
手元の白いハンカチを眺めて笑う。
無地で白いハンカチっていうのは今時珍しい。探すのに苦労した。
「それ、俺のだよね?」
横手から覗いてくる男の目から隠すように私はそのハンカチをしまった。
「何の話?」
聞き返せば、彼は明るい色の髪をガシガシ掻く。
やれやれ仕方ないなぁって顔をしたあとに、
「……別にぃ」
微笑とも苦笑ともとれる顔。
きっと彼は全部分かってるんだろうと悟る。
「今日は夕日でも見て帰る?」
ほら、やっぱり。
「うん!屋上以外で、ね」
「はいはい」
面倒くさそうな返事の割りに、顔には笑み。
「私、その顔好き」
「顔だけデスカー」
「全部デース」
ふざけ合って一緒に帰る。
夕焼けが近づく青い空と、つながれた手と彼の香りに、らしくもなく“幸せ”ってものを感じた。
+++あとがき+++
人のしたいこととかしてほしいこととか過敏に感じ取って実践してくれそうですよね、佐助って。
恋人じゃなくてもいいから、そういう人が近くにほしいなぁと思います。
※バックブラウザ推奨
2008.06.22