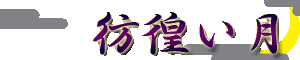色のある記憶
松永さんがやたらと絡んでくる。
何を企んでいるんだろうと最初の頃は不思議に思ったが、どうやら慣らされてしまったらしく常に隣にいる今の状態が普通であるようになった。
私としては、私の世界で唯一色を持つ松永さんの近くにいるのは満足だ。
あの不快だと感じた気配はほんの時折訪れるものの、必要以上に近寄りはせず、正体を表す気はないらしい。
あれが近づくたびに不機嫌になる私を松永さんは笑ってからかう。
「熱心なことだ」
「いい加減にしてほしい」
感じた気配に松永さんは笑みを、私は眉間にしわを寄せる。
松永さんの立てたお茶をいただいている最中だというのに、またあれだ。今日は珍しく私が菓子作りをして――何故できたかは身体の癖、のようなものだと思う――出来を褒めてもらった直後だというのに不愉快な。
「気になるかね?」
「不快」
あの気配を感じると胃の辺りがざわつく。
胸がつぶされるような圧迫感を感じる。
落ち着かない上に、気持ち悪いこと、この上ない。
「卿は相当アレが気にかかるようだ」
妬けてしまうね、と続けられた言葉は理解に苦しむ。
そもそも、妬ける、などという感情をこの人は持っているのだろうか。
いつも通り口の端をあげるだけの笑みを浮かべた彼はいまだ笑い続けている。
「こちらに来たまえ」
今でも充分気がするが、言われたように私は松永さんに近づく。
と、またも強引に松永さんは私の手を引いた。
コレばっかりだな、この人は。
松永さんの腕に収まって、彼にしては非常に珍しく私の頭を優しく撫でてくる。
優しいなどという言葉に、縁もなさそうに見えるのに。
「少しは落ち着くかね」
言われて、不快感が消えていることに気付いた。
まだあの気配は近くにある。
だというのに、胃や胸に感じる違和感や不快感が消えていた。
そういえば、あの気配がするときに松永さんは決まって私を近くに呼ぶ。
「……松永さん」
落ち着く。
松永さんの近くは、居心地がいい。
世界は色鮮やかになるし、落ち着く。
「貴方は何者?」
「これはこれは、卿には既に名乗ったはずだが?」
至極おかしそうに、身体まで揺らして笑う彼の笑みは弾んでいた。
いつもの、顔だけの笑みじゃなく、口だけの笑みでおなく、本当に面白いといったような、笑み。
柄にもなく、爽やか、という文字が当てはまるような気がした。
「何か失礼なことを考えているだろう」
「……貴方は実に興味深い」
「ククッ、それは結構なことだ」
気配が消えたところで、私は解放される。
立てたお茶の泡が全て静まり返ってしまっていた。
中身を捨てて、茶器を始めの状態に戻す松永さん。
「さて、卿の作った残りの生菓子もいただこうか」
ちゃっかり、作ったのが一種類だけでないとばれている。
クスリと笑う松永さんに、誰かの顔がダブった。
『の作る菓子は旨いな!――の上を行く!』
『ちょっとちょっと、――の旦那ってば菓子作りで忍を競わせないでもらえますかね』
「――ッ!?」
笑顔、赤、明るい声、呆れ顔、緑、日差し、縁側、菓子、団子、誰かの、私の……。
様々な色が、目の前にあるわけでもないのに溢れる。
眩暈と、胸を鷲掴みされたような動悸の激しさに膝が折れる。
そのまま畳みへと倒れこむかというところで、冷たい手が私を支えた。
「ッハァハァ」
なんだ、今のは。
なんだ、わけが分からない。
何が、どうなって、何の覚えも、でも記憶が。
「」
冷たい声に、冷たい手に、段々と落ち着きを取り戻す私がいる。
先程見えたのは、おそらく私の、記憶。
記憶の欠片。
落ち着けば、答えなど簡単に出るというのに。
「卿は、何が欲しい?」
耳元で囁かれる誘惑。
「……もう少し、このまま」
すがりつくように松永さんの服を握り締めれば、それに応えるかのように抱き寄せられた。
ああ、松永さんも心の臓、動いてるんだな。
今は、今はこのままで。
落ち着くこの場所がいい。
※バックブラウザ推奨
2008.08.01