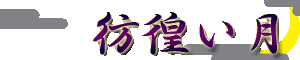裏山登山
木の葉が紅く染まることを紅葉と言うが、いちょうなどのように黄色に染まる場合は果たして何と呼ぶのだろうか。黄葉?だとしたら語呂が悪い気がしてならない。
そんなことを考えながら私は縁側から庭の向こう側に見える山を眺めていた。山は紅く染まっていて、私には赤い塊にしか見えない。
ちなみに現在進行形で朝恒例の殴り合いが目の前で行われ、ドカァとか、バキィとか、人として不味いような音が響いているが、私のとなりには口は悪くとも行動は紳士?の佐助がいるので、例え幸村が吹っ飛んでこようともきっと安全だ。
「山一面が武田色ですね」
「武田色って、……まあ、そうね」
佐助は私の言い回しに何か突っ込みを入れたそうにしていたが、結局は賛同してくれた。入れてもらって全然構わないのだが、私のボケに付き合うと疲れるだけだと学習したらしい。
何とはなしに先程の疑問をぶつけてみると「そんなん別にどうでもいいじゃん」などと、本当にどうでも良さそうな声音で返ってきた。
「ぅぉおお館さばあああぁぁぁーー……」
本日最大級のラブコールにドップラー効果を聞かせながら、幸村はちょうど山の方向へと飛んでいった。
いつも思うがどこまで吹き飛んでいるのだろうか。ゲームのムービーでは星になるくらいだから宇宙まで飛んでいたらいいなと思う。それはさすがの幸村も死んでしまうだろうか。
と、地響きがして雄叫びが聞こえて、おぉ、帰ってきたきた、と思う。
「今日もよく飛びましたね」
「そーねー」
「殿ぉ!見ていてくださいましたか!?」
お館様にスライディング土下座をかまし、次に私の方にくる。
若干身構えたような佐助の気配が次には呆れを醸し出したような気がした。
幸村が、ガッと掴みかかってくることなく私のとなりに普通に座ったのだ。いつも突っ込まれる度佐助にお姫さま抱っこで助けられていたため若干惜しいような気がするが、まあ彼も学習したと言うことだろう。
「見てましたよ〜」
見えているかどうかは別として、私は赤に微笑む。
「山の方でしたけど、紅葉はいかほどでしたか?」
……………。
おや、返事がない。ただのしかばn……げほんごほん。
「真田様?」
「あ、いや、木々が赤々として燃えたぎるようでござった!」
いや、燃えたぎったら山火事になるだろうよ。などという突っ込みは抑え、そうなんですか、と再び山の方へ目を移す。もしかしてあの赤いのは山火事でも、と思って、いやいやと顔をふる。
というか、幸村よ、あんたはどこまで飛んでいってるんだ。
「よし、では行くぞ幸村、佐助!」
「はっ!もちろんでございまする!!」
「はいはい、大将のご命令とあらばっと」
「はぃ?お出掛けですか?」
何か急に意気込み始めたぞ。
武田の人間は大体にして突然すぎる。殴り合いの始まりもそうだし、佐助の登場の仕方もまた然り。いい大人だろうに落ち着きのない人たちである。
「紅葉狩りじゃあ!支度せい、!」
「え、あ、はい!?」
なぜ急にそんな……いやそうだ、この人たちは突拍子もないのだ。仕方ないのだ。
あれよあれよという間にお館様、幸村、佐助、そして私というメンツで山を上っていた。
……徒歩で。
始めは馬で行こうとしたらしいが、私が馬に乗れなかったがためにお館様と幸村が「山を上るも鍛練のひとつ!」「さすがでございますお館様!」などと騒ぎだし、佐助が止めるかと思いきや「いいんじゃない、俺様馬より早いし」と自慢染みてかつ肯定の言葉なんぞを発したせいである。誰か乗せろ。
徒歩で歩くことに反対しなかった私が悪いのだろう、きっと。
おかげで山を登り始めて数分もしないうちに私は木の根や地面に躓いてよろけ、躓いてよろけを繰り返すはめになった。
そのたびに佐助が素早く助けてくれるので大事には至っていない。が、そろそろ申し訳なくなってきた。
「ご、ごめんなさい……」
「いやこっちこそ。ちゃんが鈍いのにこうなることを予想してなかった俺様たちも悪いさ」
鈍いって、ほんともうどストレートだな、この男。
「手を繋ぐか抱き上げるかどっちかしたいとこだけど」
「破廉恥であるぞ、佐助!」
「って言われちゃぁなぁ」
手を繋ぐのが破廉恥だなんてさすがは幸村である。
お館様はそんな私たちを見て笑っているだけだ。おおらなかんだかなんなんだか。
「もうしばし辛抱せい。すぐ見晴らしのよい場所に出ようぞ」
カッカと笑いながらいうお館様に続いて山をひたすらに上れば、見張らし台のようなところについた。
ほう、と思わず嘆息が漏れる。
山の紅葉と空の青、城下とおぼしき町並み。
美しいなどと口に出したら恥ずかしい言葉が似合う、そんな風景だった。
そこから振り返った山もまた壮大だった。
「綺麗な赤ですね」
「これならたくさんの紅葉が採れましょうぞ!」
え、採るの?
思わず全員が幸村を見ていた。
「見ていてくだされお館様ぁ!!」
ノリノリで彼は去っていく。紅葉の紅に幸村の赤が混じって私にはもう識別不可能だ。
しん、とその場が静まり返る。
「私の常識力が正常なら、紅葉狩りって紅葉を愛でることだとばかり思っていたのですが」
「うむ」
「間違ってないから安心していいぜ、ちゃん」
ですよねー。
よかった。魔法のスペル『BASARAだから』でこの世界の紅葉狩りが本当に紅葉を採る行事じゃなくて。
あはは、と苦笑しながら私は再度紅葉を眺める。
「お館様も、猿飛様も散策してきてくださいな。私はここでのんびり休ませてもらいますので」
「ではわしも紅葉でも採ってくるかのう」
「んじゃ、俺様ちょっと旦那探してくるわ」
笑いながらお館様も佐助も去っていく。
あー、お館様が本当に紅葉採ってきたらどうしよう。いや、その前に幸村か。でも佐助が見に行ったみたいだし、大丈夫だろう、たぶん。拾った落ち葉なんて漫画の世界の中で焼き芋を焼くくらいにしか役に立たないのになぁ。
空を仰げばやはり赤がある。手を伸ばして、でもそれすらもぼんやりとしていて、私の知る紅葉の形をそこから見い出せないでいる。
「見えれば、もっと綺麗なのかな……なんて、ね」
思ったより見えないことって凹む。しかも完全に見えない訳じゃなくて、ちゃんと見たこともあるのにそれが打開できない悔しさ。
近づけば見える、かな。
少しだけなら、ここを離れても大丈夫だろう。すぐそこの木の下に行くくらいだし。
見張らし台から降りて一番近くの木の下に向かう。
手を伸ばして石橋を叩きながら距離感を掴み、進む。
が、石橋を叩いて渡っても石橋が壊れてしまっては仕方がない。要はこけました。はい、こけましたよ、ケッ。更に数回前転やら横転やらしましたが、なにか。
「いったぁ……」
久しぶりの痛みに顔をしかめる。
最近は屋敷の中ばかりだったこと、転ぶといつも佐助が支えていてくれたことを思い出す。
いやもう、ほんとなにやってるんだか。
立ち上がって確認するとお館様にもらった着物汚れてしまっている。髪に手をやれば、ギリギリセーフ、幸村にもらった簪は辛うじて髪に引っ掛かっていた。落ちそうだったので引き抜いて胸元に入れておく。
転がってきたところを見上げてため息一つ。
「……ヤバいなぁ……」
ちょっと着物では上れそうにない急斜面だ。たくしあげれば頑張れるかもしれない。が、前方視界不良のため掴まないと上れないところを掴み損ないそうだ。手もまだ完治とはいえないし。
やれやれと私はそこに寝転がった。紅葉の赤から見える空が高い。
「眠……」
最近早起きだからなぁとどうでもいい感想を抱きながら私は目を閉じた。
人間、寝ているときの時間というのはあっという間で、起きたときには空が赤かった。
「うっわ」
佐助に見つかりでもしたら説教ものだろうか。一時間、いやそれではすまされなそうだ。と、考えてはたと気付く。
探してくれるだろうか。
向こうからしたら突然現れた変な女というだけで、いなかったらいなかったで、穀潰しが減るわけだから、特にデメリットもない。
まあ来た当初から樹海に行こうとしたわけだし、こんなところでのたれ死ぬのも私らしいかもしれない。餓死かー、この季節だから凍死も行けるだろうか。うん、洒落にならない。
起き上がって赤い空と紅い紅葉を見上げ、私はそっと口を開いた。久しぶりに、歌った。
私の世界なら、そこそこの人が知っていて、カラオケに行けばあるような少し寂しい秋の歌。
でもきっと、この世界では誰もが知らない、そんな歌。
平坦なところと、サビとを、たぶんカラオケの速度を一番遅くしたようにゆっくり歌う。久しぶりに聞く自分の歌声はやっぱり上手いとは言い難かった。
「ちゃんッ!!」
「ひぎゃあぁあっ!?」
突如として名前を呼ばれて思わず訳の分からない悲鳴があがる。私よ、ひぎゃあぁあってどんだけ色気がないんだ。
叫んだついでにビクついて、不可抗力でよろける。そこを誰かに抱き止められた。
その温度は暖かくて、
見開いた目の前は迷彩色で、
「はあーーっ、」
腹の底から吐き出したようなため息は何度も聞いたことがあって、
肩を捕まれて上を向くようにされて、見上げた先は人の肌色と、私を貫く赤茶と、風になびいて空と混じる鳶色。
さすけ、だ。
「何してんだ!大将も旦那も、この俺も!どんだけ探したんだか分かっ、て……る…?」
探して、くれた。
何もできない私を、探して。
急に視界がぼやけてきて、いやそこまで目は悪い訳じゃないと自分に言い聞かせるけれど、そのぼやけは視力から来るものじゃないと分かると余計に目の前の佐助が歪んだ。
「あ、あれ?おっ、かしいなー、すみません、なんか、止まらなくて、あ、はは……」
カッコ悪いことに、ぼろぼろと涙が溢れて止まらない。ぬぐってもぬぐっても洪水でダムが決壊したかのような勢いで私の目から流れる涙が止まらない。
込み上げてくる衝動を、抑えられなくて、しゃくりあげる声も止められそうにない。
ぎゅっと、暖かいものに包まれる。目の前に戻ってきた迷彩をしっかりと握って、私は佐助にすがり付いた。
やっぱり佐助って暖かい。
「どうしてじっとしてられないかねぇ、このお姫さんは」
苦笑が降ってきて、頭を優しく撫で付けられた。すみません、と謝ったつもりがくぐもってやたら醜く私の耳に帰ってきた。
涙が収まるまでひたすら佐助にしがみついて、佐助は私が泣き止むまで抱き締めていてくれた。落ち着いたときにはもう空は暗かった。
「落ち着いた?」
「はい……すみません、鼻かんでいいですか」
「ダメに決まってんでしょ!?」
迷彩ポンチョを掴みながら言えばガバッと引き離された。軽い冗談なのに。
「ほら、これ使いな」
白い布を差し出す佐助に母のデジャヴを見た気がした。受け取ってありがたく涙や鼻水をぬぐわせてもらう。
「それで、なぁんでこんなところにいるのかな?」
「紅葉を……採ろうとして」
「旦那たちと一緒になって何やってんの」
「……手にしたら、形が見えるかと思ったんです」
小さく言えば、長いこと沈黙したあと、「そっか」と返事がきた。
一瞬、佐助が消えて、またすぐに現れる。
「ほら、コレあげる」
手のひらに置かれたそれは、
「も、みじ?」
呟けば手の中で赤が風に揺られた。
「猿飛様、ありがとうございます」
「……さっさと帰るぜ。大将も旦那も心配してんだから」
「はい!」
紅葉を壊れないようにそっと握りしめて、私は始まりのあの日と同じように差し出された手を取った。
※バックブラウザ推奨
2008.04.23