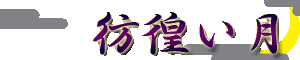(日常+現実)崩壊
〜生活の知恵〜
KAITO――呼びづらいので以後はカイトと言おう――の同居も決まり、未だつけっぱなしのパソコンに気付く。
「じゃあとりあえず……なんか歌ってもらおうかな」
私の言葉にカイトは更に顔を輝かせる。
買ってきた楽譜を取り出して機械に打ち込む。もちろんサビの部分だけ。
音楽には疎いけど小学校の授業で一応音符は習ったし、パソコンは多少使えるので苦労はしない。
……とは言っても慣れない打ち込みはたった15秒ちょっとのサビの部分に一時間強をかける。それを飽きもせず横で見ていたカイトの忍耐力は中々のものだと思う。
「はい、どーぞ」
「はい!では……」
カイトは嬉しそうに笑ってパソコンに手をかけ、目を瞑る。…ここはどんな原理だとか突っ込んではいけないところなのだろう。
その口から流れ出した歌は私が打ち込んだ通りを正確無比になぞっていた。
「どう…でしょうか?」
「ああ、うん。音痴だった」
私の言葉にカイトはがっくりと、それはもう漫画のように見事にがっくりと項垂れる。
だってノンブレスかつ平坦声は……音痴、と表現するしかない。
「ごめん。私の修行不足が原因だね」
例え実体化してもカイトはソフトウェア。制作者の言われた通りに動くだけなのだ。彼が音痴なのは私に非があると言って過言ではない。
むしろ、入力された音を外さずに歌ったカイトはすごい。
となると、うまく歌わせるには1音ずつの設定が鍵になるわけだ。日本語ではなく中国語の四発音っぽく考えた方がよさそうだ。
……確かに、これを調教と呼ぶのも言い過ぎじゃないな。あの短時間でサビだけ出来ただけでも上出来だな。
「マスター?あの……」
「うん、お腹が空いた」
「はい?」
考えすぎてお腹が空いた。
私はパソコンを落とすと夕飯作成に取りかかることにした。
「カイトは好き嫌いはある?ていうかその前にご飯食べる?」
キッチン――というよりただガスとシンクが並んでいるだけの通路――に立って尋ねる。
パソコンを切っても動いているカイトが不思議だ。何が動力源なんだろう。
「あ、え、えと……分かりません」
「だよね。とりあえず食べてみてダメなようなら違うの考えようか」
冷蔵庫から材料を取り出す。
スクランブルエッグを塩コショウで作って置いておく。鮭の切り身の残りをバラして、冷凍してあったご飯と炒める。ちょっと醤油を垂らしてから、その中にスクランブルエッグを戻す。簡単な鮭チャーハンだ。ハムもニンジンもないけど文句言わせん。
「カイト、こっち来て。はい、ちょっと味見」
「は、はい!」
小皿に軽くチャーハンをよそって渡す。
カイトはそれを暫く見つめて、意を決したように口にした。
「あ、美味しいです」
「そ?物は食べれそうだな」
二人分作るとなるとこれから食費がかさむかも……。ちょっとバイトの時間増やそうかな。
「カイト、これそこのちゃぶ台に持ってって」
皿に盛り付けたチャーハンを渡す。彼は言われた通りにそれをちゃぶ台まで運んでくれた。
ペットよりはましだな。
次に鍋に水を入れて火をつける。暖まる間に今ある野菜で適当にサラダを作ってそれもカイトに渡した。
鍋の水がお湯に変わる頃、だしの素と醤油、コンソメでスープを作る。味は相変わらず薄いけど贅沢言えない。
すべてをテーブルに並べてカイトにフォークとスプーンを上げた。ちなみに私は箸。
「皿から直接食べちゃって」
「はい、マスター」
悪いが茶碗は買ってないし、食器も一人分ずつしかない。
「じゃ、いただきます。カイト、モノ食うときはいただきますっていうんだよ」
「あ、はい。いただきます」
……私は子育て中の母親かなんかか?いや、考えないようにしよう。
「マスターの手料理、美味しいです」
はぐはぐと頬張って言うカイトはまたも笑顔。
手料理なんていつものことだけど、そう言われるのは新鮮だった。誰かと一緒に食べるご飯も久しぶりだ。
結構、いいものかもしれない。
「ありがと」
呟くとにっこりと笑顔を返された。
聞こえないように言ったつもりのお礼の言葉を彼の耳は拾ったらしい。
ご飯の後はさっさと洗い物をして、洗い物の仕方をカイトに仕込む。
水は桶に溜めながら使うこと。
無駄に水を流さないこと。
出すときは少しだけ。洗剤も少しだけ。
「以上。破ったらアンインストールするから」
「は、はいっ!」
するつもりは今のところないけれど、破ったらマジでするかもしれない。DTMは娯楽だが洗い物にかかる水道代は死活問題だ。
死活問題といえば、これから先……どうしたものか。
カイトに留守番させるのはいささか不安がある。
私はちゃぶ台をどかして寝るためのスペースを作りながら思考する。
何で不安があるか?愚問だ。何故ならこのセキュリティの欠片もないボロアパートは変な勧誘が多い。右隣のじいさんは聞こえないふりをしてやり過ごし、左隣の奥さんは日中はパートに出ていて不在のため回避可能。かく言う私もバイトと学校で朝から夜までいないため今まで出会ったことはあまりない。
だからと言ってカイトを学校やバイト先に連れているわけにも行かない。
やはりカイトには留守番をしてもらうしかない。
「マスター、洗い物終わりました」
カイトがキッチンからリビングへ帰ってくる。
「ああ、ありがと」
「……何をしているんですか?」
「ダンボールを敷いている」
「…………それは、見れば分かるんですが……」
私の行動が理解しがたいとばかりにカイトは困惑した目をこちらに向けている。
別に好きでダンボールを敷いているわけではない。
「こうでもしないと、うちの煎餅布団じゃ寒いの」
ダンボールは敷くだけで結構暖かいのだ。何枚か重ねればそれなりにマットレス代わりになる。
ひとり増えたせいで今日はダンボールがいつもの半分だ。寝心地がいつもより落ちるのは否めない。
「マスターは生活の知恵をいっぱい知ってるんですね」
キラキラ光線でも飛ばしてきそうな、カイトの無垢な視線が痛い。何も知らないって、怖い。
「はい」
「はい?」
バスタオルひとつ、カイトに渡す。
カイトはそれを受け取ったまま首を傾げた。
「先お風呂良いよ。お湯使いすぎたら……どうなるか分かってるよね」
「はひっ」
目を細めて言ってやると逃げ込むようにお風呂場――というほどでもない狭いユニットバス――に駆けて行く。そんなに怖い顔をしていただろうか。
でも、生活がふたりになる分いろいろなところで節約しないと不味いのは確かだ。節約術を今のうちに仕込んでおかなければ。
カイトがお風呂している間にさっさと布団を敷いてしまう。
明日の支度をして、私もお風呂に入る準備をする。
「マスター、ただいま上がりました」
丁度よくカイトが風呂から上がってきた。気持ちよかったのかお風呂場に駆け込む前より表情はにこやかだ。
あまり水音も聞こえなかったし、ま、合格でしょう。
「じゃあバスタオル貸して」
バスタオルを取り上げて、代わりにフェイスタオルを渡す。
「ちゃんと髪の毛乾かすように」
ドライヤーないけどね。あれ電気代かさむんだ。
頷いたのを認めて、私は着替えと取り上げたバスタオルを持ってお風呂場に向かう。
「え、あの、マスター?」
遠慮がちなカイトの声に振り返る。
フェイスタオルからわずかに顔を出した彼の顔は赤い。
「何?」
「それ……俺が使ったやつですけど……」
「うん、知ってる。うちバスタオル二つしかないから」
二つ一気に使うと次の日使えるものがなくなるんだよね。今日はタオルケット代わりにも使いたいし。
「ちなみにそのフェイスタオルも借りるから」
言うだけ言って私はお風呂場に入った。
もちろん顔を赤くして硬直していたカイトには気付かなかった。
+++あとがき+++
第二段ー。生活の知恵を活用しましょう♪
※バックブラウザ推奨
2008.02.16