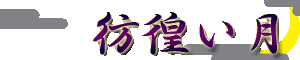沈黙の歌姫 〜憂〜
アルメイダの村で一泊し、午前中に戻った二人は国王に報告を済ませ、リオンは客員剣士に用意されている執務室に向かった。その後ろを
が歩く。
(相変わらず城での視線が痛い……というかリオンと一緒だから更に鋭くなった気がする)
わずかに眉間にしわを寄せる
。
依然城に厄介になっていたときもミライナがよく構ってくれてはいたが、所詮よそ者、所詮クチナシ。更に細い身体なのに理不尽にさえ感じる戦闘力の差。
妬み、羨望、僻み……兵士たちが
に向ける視線は決して暖かいものではなかった。
「おい、報告は済んだ。先に帰っていろ」
城の玄関口付近でリオンに声をかけられた。
「(あ、うん)」
突然のことに一瞬反応に遅れるが、言われたとおりにこくりと頷いて
は城を後にした。
その後姿をしばし眺めてからリオンは歩き出した。
『まったく、あんな不躾な視線あてられたら気が滅入っちゃうよ。
そう思いませんか、坊ちゃん』
喋り出すソーディアンシャルティエを黙っていろ、と軽く小突く。
「元気でやっているみたいだな」
かけられた声にリオンが視線を巡らせれば、そこには鎧を纏った女、ミライナがいた。
そういえば彼女があいつを拾ってきたんだったと頭の隅で思う。
「ミライナ様」
軽く会釈をすると彼女は朗らかに笑いながらリオンに横に並ぶ。
「どうだ、彼女は」
「足手まといにはなりません」
正直リオンが手合わせをし、勝てるかは分からなかった。――悔しいので口にはしない。
そして
は底が見えない。あの数十体といた魔物をすべて倒し、息切れもしない。
どの程度の実力者であるのか想像もつかなかった。
「だろう?正直私でも苦戦する。
しかし、いい顔をするようになったし、ヒューゴ殿とリオンに任せて正解だった」
言葉の意図を掴みかね、リオンはミライナを見やる。
といえばコロコロ変わる表情、そしてよく見る顔は笑顔。
「あの年で、あの実力で、いつも物憂げな顔をして、記憶もなければ声も出せない……。
は自然と異怖の対象だった。
それに私もあれこれと構ってしまったこともよくなかったんだろうな」
「物憂げ……?」
あれのどこが。とでも言いたそうなリオンの表情にミライナは微笑する。
「君と会えたことが余程プラスになったんだと思う」
ふっと彼女はリオンから視線を外し遠くを見た。
少しだけ細くなったように見える目元は優しかった。
「医者に寄れば声が出ないのは精神的なものらしい。
あくまで憶測だが……記憶に、連動しているのかもしれない」
いったん言葉を切って、ミライナはリオンを見やる。
「親心、というほど年は離れていなそうだから姉心といったところだろうな……よろしくしてやってくれ」
「はい」
リオンの返事を聞くと満足したように彼女は去っていった。
『そういえば、城に入った瞬間、雰囲気は変わりましたよね、彼女』
緩やかにシャルティエのコアクリスタルが光る。
リオンは誰にも聞こえないように「知るか」と答え、執務室の扉を開けた。
城での作業が報告書の作成だけであったリオンは、昼過ぎにはヒューゴ邸に戻った。
「(リオン!おかえりなさい!)」
「おかえりなさいませ、リオン様」
屋敷の戸をくぐると
とマリアンが満面の笑顔で出迎えた。その笑顔にミライナの物憂げだったという言葉が頭を掠める。
(僕には関係ない)
緩く頭を振る。
「リオン様、これからお茶にしようとしたところなのですが、ご一緒にいかがですか?」
「ああ」
マリアンに誘われたらリオンが断る理由はない。スキップしそうな勢いの
と微笑みを湛えたマリアンの後に続いて庭に出る。
庭に設置されたテーブルにつくとマリアンがお茶を出してくれた。
「どうぞ」
「ああ」
いてもいなくてもうるさくはないが、
がいなければもっとちゃんと話せるのに、とちらりと彼女を見やる。
は非常に幸せそうな顔でプリンをパクついていた。その顔はただの少女であり、とてもわずかな時間でモンスター数十体を伏せる薙刀使いだとは思えない。
ふとリオンの視線に気付いたのか
は顔を上げる。
「(食べないの?)」
にぃっと口角が上がる。
リオンはふいっと視線を反らすと自分のプリンに手をつけた。
わずかながら幸せそうに緩む口元を見て、
が微笑んだのには気づかない。
「(ごちそうさまでした!)」
がマリアンの裾を引っ張る動作を目の端に留め、そちらを見る。
口の動きでごちそうさまと伝えている。
「お茶のおかわりですか?」
にこりと笑うマリアンに
は苦笑を返した。すると彼女はリオンを見て口を開いた。
「(リオン、ごちそうさまって伝えて?あとおいしかったって)」
「僕はお前の通訳じゃない」
すっぱり切り捨てる。
むっと、彼女は考え込むしぐさを見せた。
出会ったときに胸元から紙を出したのだからそれをやればいい、とリオンは思い、それ以上口は出さない。
「(伝えてくれたら二人っきりにしてあげる☆)」
「マリアン、ごちそうさま、おいしかった、だそうだ」
即決だった。
「まぁ、お褒めいただきありがとうございます」
マリアンとにっこり笑い合うと
は席を立った。
に上手く使われたようでリオンは居心地の悪さを感じる。
「(ありがと)」
「フン。明日は早朝からノイシュタットに行く。寝坊するなよ」
リオンが言うと
は了解の意を示し庭を去った。
「エミリオはすごいわね、何て言ってるのか分かるなんて」
「別にたいしたことじゃない。唇の動きやあいつの幼稚な動作でなんとなくわかるだけだ」
つい、と顔をそらすと、それでもすごいわ、とマリアンが褒める。
彼女に褒められるのは嬉しいのでリオンはそれを隠さず照れた笑顔を向ける。
(僕にはマリアンだけいればいい。
そう、余計なものなんて、増やさなくてもいいんだ)
自分に言い聞かすように心の中で唱え、はっきりしない感情を追い払った。
微睡む脳にふと微かな歌声が響いた。
聞いたことのないメロディ。
透き通るように綺麗で、小川のせせらぎのように優しく、包み込まれるような暖かい歌声。
意識が浮上する。視界に入ってきたのは薄暗い見慣れた天井。
「……シャル?」
寝起きの掠れた声でリオンはシャルティエを呼ぶ。
『どうしました、坊っちゃん?』
すぐに頭に響く聞きなれた彼の声。
「歌が……聞こえなかったか?」
『? いいえ?』
「そう、か」
『夢でも見たんですか?』
「かもな」
覚めてしまった頭に寝直しは無理だと判断すると、リオンは荷物の準備と確認を始めた。
ふと窓に近寄ると、隣のバルコニーに
がいた。
下限の月の光が差し込む中にたたずんでいる。
正した姿勢と不規則に動く口。喉元に当てられた細い手。
(歌、か?)
彼女の口がつむぐ音はもちろん聞こえない。ただ。その口の動きに連動してリオンの頭の中にメロディが流れる。どこかで聞いたような声で、どこかで聞いたようなメロディで。
それは夢で聞いた曲。
不意に口の動きが止まる。
その瞬間、
の顔が歪んだ。唇を噛みしめ、喉元の手を握りしめ、眉がこれでもかというくらいに寄って。
昼間の馬鹿みたいに明るい笑顔からは想像できないくらい『憂い』に満ちた顔。
(物憂げな、顔……?)
城でミライナに言われた言葉が再び蘇る。
何を思っているのだろうという疑問が胸の中に湧き上がる。
(失くした言葉か、いや、記憶……?)
考えを巡らせ、リオンは眉を寄せる。
(何故僕がこんなことを考えなくてはならないんだ)
リオンが考えにふけっている間に
は部屋に引っ込んだようだ。
何故か苛立つ心を押さえつけ、リオンはベッドに腰掛けた。
(関係ないじゃないか、あんなやつ)
いつも後ろについてきて、時々並んだかと思うと気持ちいいくらいスカッとした笑顔を見せる。
初めて出会った時も、ウエストポーチを買った時も、リオンは彼女の笑顔しか知らなかった。
彼女の
を見るたびに心が軽くなる気がした。
だが、今彼を占めている感情は……
――不安。
自分の知らない
がいる。
それだけで胸が締め付けられるようだった。
(違う、おかしい、会って間もない奴に……)
首を振ってよく分からない感情を押しやった。
その数時間後、再び玄関が分からないと泣きついてきた
はいつもの彼女だった。
Next Story...
※バックブラウザ推奨
2007.04.07