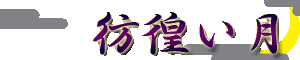沈黙の歌姫 〜友〜
リオンの目の前には先日貰ったばかりの銀色のバンクルが置かれていた。シャルティエの柄に刻まれた模様と似た模様が刻まれたバンクル。それは部下であるがリオンに寄越した、誕生日のプレゼントだった。
何故だか分からないが、の前に出るといつも彼女のペースに巻き込まれてしまう気がした。
(分かっているんだ)
リオンは分かっていた。
自分が大切にしている、愛しているただ一人の女性が自分のことを見向きもしていないことなど、分かっているのだ。
出来ることといえば心を殺し、自分の必要とされる役をこなすだけだった。
それなのに、彼女が現れた。
リオンを友だといい、道具でもなく、哀れな子供でもなく、部下でも上司でもなく対等な一人の人間として見てくれる。
いつも気がつけば半歩後ろにいる。
振り向けばすぐそこにいて目があると、微笑を返す。
『坊っちゃん?』
「ちっ」
落ち着かなくてシャルティエを手に部屋を出た。
考えがまとまらないとき、考えたくないときは剣の鍛錬に限る。
中庭に下りて、しばらくの間一心不乱に剣を振り続ける。
どれくらいしただろうか。
ピタリとリオンの振るう刃が止まる。
「シャル……」
そっとコアクリスタルに指を滑らせる。
『どうしました、坊っちゃん?』
幼い頃から兄弟のように共にいたソーディアンは優しく尋ねてきた。
気持ちをどう言葉にすればいいか悩みながら、端にある木の根に座った。
「僕は……どうすればいい?」
正直リオンは迷っていた。
大切な人、心を開ける人はひとりでいい。マリアン以外、いらない。
そう思っていたというのに、にも心を開きたいと思う自分がいる。いや、開きかけている自分がいる。
『……僕は、悩む必要はないと思います。
坊っちゃんの中では、もう答えが出ているんじゃないですか?』
コアクリスタルが優しく光る。
答えは出ているかもしれない。だが、それは彼女を巻き込んでしまうことに他ならない。
心を開きかけているからこそ、迷う。
「……………」
気配を感じ取って顔を上げる。
視線の先にはがいた。
「向こうに行け」
ギッと近づいてくる彼女を睨みつける。が、彼女は臆することなくリオンに近づいて来る。
「(一人でいたいって言う人は、一人にしちゃいけないんだって)」
にっこりと笑う。
口が動いたから何か言ったのだろう。だが、リオンには今はどうしようもなくそこにいてほしくない気分に襲われる。
「聞こえなかったのか。向こうに行け」
「(イ・ヤ)」
はっきりと肯定の言葉が伝わる。
リオンが睨むのも構わず、彼女は隣に座り込んだ。
こうなっては何を言っても無駄である。
リオンは場所を変えようと立ち上がる。が、そのマントをが引っ張った。
じろりと見下ろせば、いつものあけすけな笑顔ではなく、穏やかな微笑と優しい光と瞳に湛えた彼女がいる。先ほどまでリオンが座っていたところを軽く叩いて、座れと言っているらしかった。
「はぁ……」
リオンは移動を諦め、同じ場所に座る。
左膝を伸ばし、右膝を抱え、額をくっつける。
(何故、こいつは傍に来てくれる?何故、傍にいてくれるんだ?)
顔を伏せたまま、目だけでを見る。
彼女は先ほどと変わらない表情でリオンを見ていた。
「どうせお前も……」
呟いてふいっと顔をそらす。
(どうせ、離れていってしまうんだろう?
だったらそこにいないでくれ。頼むから……)
そっと手に何かが触れる。暖かい何か。
反射的に顔を上げれば、彼女がリオンの手を握っていた。今まで感じたことのない感触に躊躇しているとはリオンの握られた拳を優しく開き、手の平に指を走らせた。
『(そんな顔したリオン、独りにさせない)』
「っ」
『(私話せないから何でも言っていいよ。
広がる心配がないのは請け負うから)』
目が合う。真っ直ぐに、まるでリオンの心の中まで見透かしたような視線だった。
サァァァと二人の間に風が通り抜ける。
どれほどそうしていたのか、絡まった視線を先にそらしたのはリオンだった。
「お前、紙は?」
常に持ち歩いているんじゃないのか、という視線をに向ける。
『(直に触れ合ったほうが思いは伝わるものじゃない?)』
「やめろ」
リオンが言うとはクスリ、と擬音のつきそうな微笑をもらす。
「(そんな顔したリオンに言われても、ね)」
うにっと、頬に何かが埋まる感触。
手の平にいた彼女の指がリオンの赤過ぎる頬に埋まっていた。
一瞬固まって、リオンはずざーーーーーっと一気に身を引く。
その様子には大爆笑だった。
「う、うるさいっ」
実際彼女は声を発していないからまるでリオンの独り言劇場である。傍から見ればソーディアンと話しているのに近い。
赤くなっていた顔を更に赤面させ、リオンはそっぽを向く。
の前では虚勢もすべてが無駄のような気がした。
マリアンとは別の安心感を感じる。
(これが、友という奴だろうか……)
「(リオン?)」
顔を覗き込んでくるに一瞬だけ目を合わせる。
になら、教えていいと思った。
「……エミリオだ。どうせ周りは聞こえないんだろう?僕のことはそう呼べ」
彼女は首を傾げ、すぐに頷いた。
おそらく聡い彼女ならリオンが何も言わずとも呼んでくれると彼自身が分かっていた。
「(エミリオ)」
つむがれた口の形に心が和らいだ気がした。
「……何だ」
「(呼んだだけ)」
聞き返せばにっこりという文字が似合う笑顔が返って来た。
「………そう、か」
大切に思う人間が増えても、彼女なら負担にならない。
例えヒューゴに駒として利用されていようが、なら大丈夫だとリオンは思った。頭も回るし、腕も立つ。
それに。
(こいつの言葉を理解できるのは僕だけみたいだし)
それはちょっとした優越感。
『坊っちゃん』
「何だシャル」
こいつにしてはやけに大人しかったなと思い、リオンは視線を落とす。
『良かったですね』
ガシャン
『あぁ!そんなご無体なっ!置いていかないでください!お願いですから坊っちゃぁぁぁぁぁん!!』
リオンはシャルティエを放ったまま歩き出す。
それを見てはやれやれと笑う。照れ隠しであることは一目瞭然なのだ。シャルティエを両手で抱え、耳まで真っ赤にしたリオンのあとを追いかけた。
『ありがとうぅぅっ!』
きらりと光るコアクリスタルにはにっこり微笑んだ。
『(……ってもしかして僕の声聞こえてる??)』
そんなシャルティエの疑問に応える声はもちろんない。
はリオンを後ろから覗き見た。
「(エミリオ!特別な名前を教えてくれたってことは、私たち友達ってことだよね?)」
「ふん」
鼻を鳴らしてあしらわれるが、その顔には微笑がわずかに見て取れて、はにっこり笑い返した。
(マリアンに勝てる気はしないけれど、リオンの……エミリオの友達になれたって結構特別なことだよね)
ふふふ、と声にならない笑いを漏らしてはリオンの半歩後ろを歩く。この距離が、今は愛しくさえ感じられた。
それはいつもと同じに柔らかな日差しが差し込む午後のこと――。
Next Story...
※バックブラウザ推奨
2007.11.11