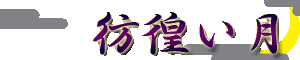千夜と一夜の物語
真っ暗な部屋。そこが私の居場所だ。
灯りもないそこに、一条の光が差す。
現れるのは摩訶不思議な私の飼い主。
「ぬし、ぬし、今日も御伽を聞かせやれ」
囀るように低音が耳を打つ。
いつからだろう、この声に安寧を覚えるようになったのは。
「あい、かしこまりました」
彼の所望する話。救われぬ話。不幸の話。
なんとはなしに読みふけった物語の中でエグイものを披露すれば、殊の外彼は喜んだ。
見知らぬ世界に放り込まれ、嬲られ、打ち捨てられ、震えていた私を「よき不幸よなァ」と笑みながら拾ったのがこの飼い主だ。
「どれ、話を聞かせて見やれ」と、とてもとても愉しそうにされていたお顔は今でも覚えている。
ひとつ、不幸の話をすれば、もうひとつ、さらにひとつ。と。
そうして私はこの暗い部屋を与えられ、彼が訪れる度、彼の携えるほのかな灯りの中で不幸の話を紡ぎ生きながらえている。
まるで千夜一夜物語。
今日は、とある男女の痴情の縺れ。
妄執を抱く女と、それに気付いて危機を覚える男。
男が幼馴染に相談をすれば、その女は病なのでは?憑りつかれているのでは?と心配される。
幼馴染と特に親しい様子に女は狂い、男と口論に。
一晩夜を明かし、男はきちんと話し合いをすべく女の元へ訪れるが何かしらに引き留められ、女の元へたどり着いたころには、女は自ら命を絶った後だった。
後悔に沈む男を幼馴染は優しく慰める。
そばにいる裏切らない、と言う甘言に、男は絆され幼馴染と結ばれる。
そうして幼馴染はほくそ笑んだ。
貴女が私から彼を奪うから悪いのよ、と。
「ヒヒッ、救われぬなァ、まっこと救われぬ」
話を終え、今回の話もお気に召していただけたようだ。
おそらくは、愚かな男の行く末を思い描いているのだろう。
「ぬしはその幼馴染をどう見る?」
「どう、とは」
「愚かか、哀れか、惨めか?」
こうして話の感想を求めてくることも、多々とある。
けれど、私は決まってこう答えた。
「どうとも」
何とも思わない。
というと、冷たく聞こえるかもしれない。
後味が悪い話だな、とは思う。
だからと言って、登場人物に対して、どうこう、と言うのはあまりない。
一本芯が通っていて、その芯の正しさは置いておくとしても、その芯に従って行動するなら、別に他人がどうこう言えるものではないし、言ったところで変わりはしない。
完結している物語に対して、ああすれば、こうすれば、というのは終わった過去に対して後悔するのに似ている大して意味のない行為だ。
「己の正しきを貫いただけでありましょう」
「正しきとな?ヒヒヒッ、妄執を、凶愛を、正しいと言うか」
「一途な想いではありませんか」
「一途…!!ぬしはまっことおかしい、やれおかしや、おかし」
ヒィヒィと笑い転げ始めたので、今日の回答もお気に召したらしい。
このお方は、私が何を言っても笑い転げている気もするが…。
笑い過ぎて噎せ始めるので、驚かさないよう柔らかく背に触れ、撫でる。
一途な思い。
一途に思えるものがあること自体、素晴らしいことではないだろうか。
感情を持つこと自体、馬鹿馬鹿しいと投げ捨てた私にとって、それは、まぶしいものだ。
つらつらと考え巡らせ背を撫で続けると、別側の手を取られ、胸の中に誘われた。
つん、と薬草臭さが鼻を突いた。
これは、初めてとられた行動だ。
包帯だらけの手が私の顎をさらい、上を向かされる。
「ぬしが今、ここに在ることがわれの仕組んだものだとしたら、この口は何を紡ぐ?」
ここに在ることが、彼の仕業だとしたら。
見知らぬ世界に放り出されたことも、嬲られたことも打ち捨てられたことも彼のせいならば。
そうだとしたら、なんだというのだろう。
「どうとも」
彼をなじれば心が晴れるか、否、そんなことはない。
今の私に晴れる心自体が在るかどうか怪しい。
何か別のことを紡げば未来は変わるか。否、変わらない。
「この口は、変わらずこの暗い部屋で、知りうる限りの不幸で救われないお話を紡ぐだけです」
彼が満足するその時まで。
どう生きたいかの欲求は、元から薄かった。
元から、親や他人の言うことばかり、聞いて生きてきた。
だから、別に、どうとも。
でも、もし、これが彼の仕組んだことで、さっきの話からの流れを組むと。
「…、もしかして、一途に思ってくださってます?」
図々しいながら飼い主に尋ねてみれば。
彼は馬鹿にしたように、けれどご満悦顔で笑われた。
暗い部屋。
そこが今の私の居場所。
彼がやってくるまで次は何を話そうか、と記憶を頼りに物語を作り出す。
最近は忙しいのか余り姿を見ないので、生きているだろうか、などと考えを巡らせたその時。
一条の光が差した。
嗚呼、来た、と目をやって、初めて彼ではない人がそこに現れた。
彼はいつもすぐに戸を閉めて、ほのかな灯りだけを頼りに私の元まで来たけれど、その人は戸を開け放ったまま、私を見る。
その人の背後から光が差し、逆光で姿かたちしかわからない。
まぶしい。
「お前が、刑部の…」
聞いたことがない声だった。
そもそも、私はこの部屋に入って以降彼の声以外を聞いたことがなかったことに後から気付く。
彼ではない誰かは私に近づき、膝を折った。
「お前が大谷吉継の妻で相違ないか」
彼の問いに首を傾げる。
おおたによしつぐ。
それは一体誰のことだろう。
つま、妻?
私はいつ結婚したんだろう。
と、いうか、まぶしい。
「…耳が、聞こえない、のか」
あまりに黙っていたからだろうか、目の前の男は不安げに言葉を紡いだ。
その呟きに首を振って応える。
「聞こえてはいます。ただ、言葉に覚えがありませぬ。
おおたによしつぐ、とは…、彼の、この部屋の所有者の名でしょうか?」
「…そうだ」
「私は……、結婚していたんですか?彼と?」
「……ワシに、聞かれてもな…」
ですよね。
困惑し始めた男に、頷く。
おおたによしつぐ、そういう名だったのか、と今更ながらに彼の名を知った。
別に知らずとも、不便はなかった。
私は物語を紡ぎ、彼はそれを聞くだけ。
そこには男女の関係とやらは、なにもなかった。
彼のことだ、いい年して結婚しないのかと言われて、面倒になって、もういる、と勝手に私を表向き妻役に仕立てたのかもしれない。
「先程の問いですが、私では答えかねますので、彼に聞いていただけると助かります」
「…刑部は、大谷吉継は、先の戦の敗将。この世にはもういない。それを、言いに来た」
はいしょう、その意味はともかくとして。
この世に、いない。
つまり、彼は、死んだ、と?
「あら、まぁ…」
ポロリとこぼれた言葉がそれだった。
空気が抜けるように、私の中から何かが消える。
名を知った途端に訃報とは…。
「…何も、知らなかったのか?」
若干憐れむ色を含んだ問いを首肯する。
彼が何者かも知らず、名さえ知らず、そして、知らない間に死んでいた。
そうして放られたままの私の元にこの目の前の男が知らせを持って来た、と。
来たところで、私はこれから先どうしようもないのだけれど。
不幸が大好きなあのお方のこと、きっとあの世で私の不幸を引き攣るほどに笑っているに違いない。
「私は、この部屋へ入れられて以降、出た試しがありませんので」
だから、今の戸を開け放たれたままの状態でも、目が痛いほどにまぶしい。
目の前の男は、そうか、と一つ呟く。
「ここ以外に行くあては?」
聞かれて首を振る。
もとより身内などいていないようなものだ。
川べりに打ち捨てられていた身が向かう宛などない。
再度、そうか、と男が呟いた。先程よりもしっかりと。
「お前の身はワシが預かろう」
そう言って男は私を軽々抱き上げる。
そういえば、何年もまともに歩いていなかったように思う。
「名乗りが遅れたな。ワシは徳川家康だ」
よろしく頼む、と続けられた言葉は耳の右から左へ抜けていく。
とくがわいえやす。
その名前はあまりに有名すぎて私でも知っている。
徳川幕府の創始者であり、今後長らく続く江戸時代の礎を築いた歴史的人物。
つまり、ここは、戦国と江戸の狭間の時代、なのだろう。
今更ながら、とんでもないところに来たものだ。
「お前の名は?」そう問われて、口を開け、閉じる。
向こうでの名前など、ここではきっと何の意味もない。
「ありませぬ、彼には、ぬし、とだけ。
名がないと不便と言われるならば、名をくださいませ」
「え、ええと、そうだな、ワシは女の名には疎い。少し考えさせてくれ」
「あい」
彼のように返事を口に乗せたところで、彼に、おおたによしつぐに名をねだれば、きっとするりと出てきたんだろうな、などと思いを寄せた。
横抱きに抱えられたまま、暗い部屋から明るい外へ。
あぁ、まぶしい。
部屋を出てすぐの庭。
四季の彩り溢れる場所。
この景色を愛でながら、傍にとくがわいえやすではなくて、彼がいればよかったのに。
そう思った心に気付いた。けれど、それは向かう宛がない気持ちであることもわかっている。
そっと瞼を下ろすと共に、気持ちに蓋をした。
B面へ
2014.02.13