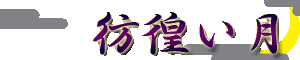考察する賢者
昨日今日と珍しく君が日が暮れきる前に戻ってきた。
以前に風呂場周りの使い方は聞いていたし、テレビで流れるドラマとやらでも度々出てきていたので今では使い方もわかるし、彼女のいない間に湯あみを済ませることもある。
時間短縮、なのだろう。音を聞く限り君は基本、湯船につからず、あのシャワーと呼ばれるもので体を洗い流すのが常だ。
それが昨日今日と、早く帰ってきたからか湯船に湯を張っているらしい、と気付く。
気付いたのだが、しかし。
「どうされましたか、半兵衛様」
三成君に声をかけられ、うん、と頷く。
「いや、今日はやけに水の音が酷い、ように感じてね」
湯船に貯めるときも、そんなに音はしなかったように思うが。
「ああ、湯船に貯めながら入っておるのでは?」
吉継君が言わんとしていることは分かる。その点については、同意なのだけど。
「それにしては……、」
普段、疲労困憊で家に帰る彼女のこと。いや、もしや、と思いながらもニュースで時折流れるニュースの一端に、風呂場で溺死の文字を思い出し、否まさかと思いながらも嫌な予感がぬぐえない。
杞憂ならばそれでいい。
けれど、彼女がいなくなっては困る。具体的に言うと金銭的に困る。
立ち上がって、風呂場へ続く戸を叩く。
「君?」
少し大き目な声をかけるが、反応は、ない。いや、まさか。
「半兵衛様、失礼します」
「三成君、さすがに開けるのは…」
ガチャ、と三成君が戸惑いもなく風呂場への戸を開ける。
水、否、湯が盛大に洗い場へと溢れている。溢れるもとは当然湯船であり、その中には君が突っ伏した状態で浮いている。
「「……」」
杞憂が現実になった。とはこのことだろう。
「君!?」
「半兵衛様、濡れてしまいます!ここは私が!」
風呂場へ踏み入れようとした僕を押しとどめて、バシャバシャと湯の溢れる浴場を三成君が突っ切る。
そしてあろうことか彼女の頭部の髪をそのまま掴み、水面から力づくで顔を上げさせた。
思わず止まる。
…それは、ちょっとないんじゃないかな…。
「貴様、我々の手を煩わせるなと言っただろう!!」
「げほっごほっ」
「聞いているのか!」
「三成君髪は止めてあげなさい、女の子だから一応」
止めれば、「はっ」と言う返事と共に今度は首を片手でつかみ持ち上げた。
…いや、そうじゃ、ないんだけれど。
三成君は女性の扱い方が壊滅的によろしくない。帰ったら何とかしよう。これでは石田家が滅んでしまう。それはよろしくない。豊臣の今後を考えればなおさら。
「…うんまぁいいから、お湯を止めて。それからこれで拭いて、君も」
「お手を煩わせ申し訳ありません」
指示通りに動いて、ようやく君の救出まで至った。
二人の体を拭いて、君の体はバスタオルで包み、三成君に運ばせる。きちんと、横抱きにするように指示をして。
居間とも呼べない共有部屋に戻れば、吉継君が呆れた顔をしてすべてを察した。
「風呂場で溺死か…不幸な話よ。息はしておるのか?」
「残念ながらな」
「一応家主だから生きててもらわないと困るよ。
この世界の人間はどうやら死んでその場に放置、というのは大騒ぎになるようだしね」
バスタオル姿の君を布団のおろすように指示をして上から掛け布団をかける。
先ほど三成君が首を思い切り掴んだ成果なのか、水は吐き出し終えていて呼吸は確保されているようだった。
特に異常もない、そう判断を下した直後。
「……っくしゅっ」
小さなくしゃみとともに君の瞼が上がる。
自然と三人の視線が彼女へ集まった。
「…おはようございます、あれ、裸?どおりで冷えると」
「君が風呂場でうつぶせに突っ伏していたのを発見して救出してあげた僕らに何か言うことは?」
ぼーっとしながら視線を彷徨わせ、最後に僕と目線を合わせると、へらり、と笑った。
「私が死ななくて残念でしたね?」
「いや、死なれたら困るから」
冗談のつもりかもしれないが、全く笑えない状況だ。
あはは、と誤魔化すように声を出して笑い、ぺこりと頭を下げた。
「お手数かけてすんませんでした、ありがとございます」
「君も少しは休みたまえ」
僕の掛けた言葉にふむ、と少し考える素振りをする。
君は頭の回転は人並みかそれ以上はある。おおよそ仕事の算段でも計算しているのだろう。
「……あと、10日は無理ですね。
ああでもアレを仕上げないといけないし、報告書も出さないと売上処理が。
ちょっと当分無理です。
あ、あと明日から出張行くんで2,3日いません。
お金先に支給しときましょうか。あとはなにか…、あ、出張準備しないと、」
「引き留めた僕が悪かったから早く温まり直してきなさい」
仕事の話を思い出したついでにとずるずる出てくる彼女の今後の予定。
仕事はできるだろうに、量が多い。彼女の容量を優に超えている、とは思うのだがこれをきちりとこなしているらしい彼女は有能なのだろう。
会社、と呼ばれる組織がどのようなものかいまいち理解に乏しいが、彼女が倒れればそれこそ傾くのではないだろうか。
それすらわからない上の者……彼女曰く狸とやらは余程、使えない頭をしているに違いない。もっと生かさず殺さず手玉に取れば今よりよく転がるだろうに。
ゆるゆると再度風呂場へ温まりに行った彼女の背を見送りながら、
「……もったいない」
そう、小さくこぼす。
もし僕の世界にも彼女がいたのなら、見出して、磨いて、三成君や吉継君を支えられる程度までには育て上げられる自信はあるのだけれど。
喉の奥の違和感に、同室の二人に気付かれない程度のため息をつく。
…ないものねだりだなんて、らしくないな。
<Prev Next>
back
2014.05.06